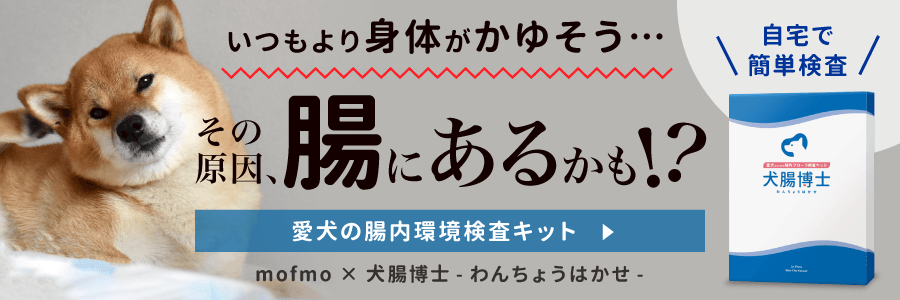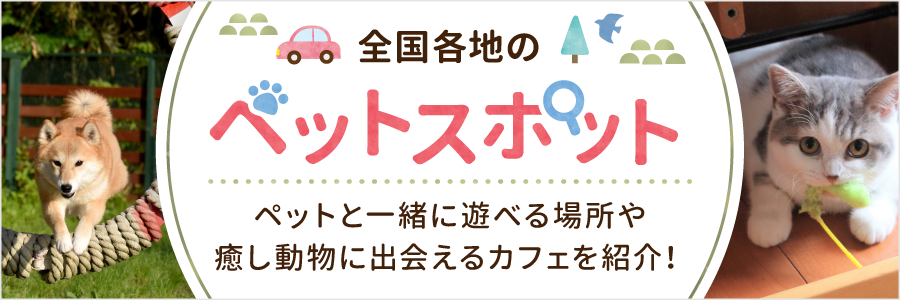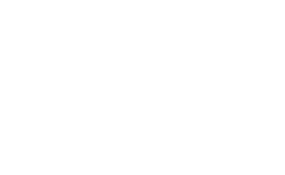犬に『離せ』を教えよう。しつけの方法のコツをご紹介。
犬とおもちゃで遊んでいるとき、ほとんどの飼い主がこの悩みを持っていると思います。それは、犬がおもちゃをずっと離さない。飼い主が犬に何をしようがおもちゃを離さない犬に、「離せ」を教える方法を伝授いたします!

離せのしつけ方法
さて、本題の犬の離せのしつけ方法です。まず犬とボール遊びをし、ボールを自分のところに持って来させます。
この際、自ら犬のところに行きボールを奪い取るような方法は厳禁です。そうすると、犬はボールを取られると思い、逃げてしまいます。 そのため、犬の名前を呼びながら後ろに下がっていくと犬は少しずつ寄って来るようになります。
ボールのヒモをつかむことが出来たら、「離せ」とコマンドします。犬はもちろんボールを離しませんので、ボールをつかんでないほうの手で犬の口に手を入れ、犬の口をこじ開けます。
ボールと口との隙間を作り、ボールを離したところで、思い切り犬を褒めてあげ、ご褒美としてまたボールを投げてあげましょう。
この方法を行うことで、犬は「ボールを奪い取られたわけではなく、ボールを離したらまたボールで遊んでくれる」と認識をします。 この方法を続けることで、犬は何をくわえていようが、離せのコマンドで物を離すようになります。
犬の力が強い場合
成犬や大型犬の子犬では、犬の噛む力が強く手で口をこじあけることが難しいことがあります。
このようなとき、口をこじ開けることに手間取っていると犬に噛まれるおそれがあるばかりか、犬は急所である口に触られる不快感やボールを取られてしまうという不安から、ムキになってしまうことがあります。
しつけは飼い主も犬も楽しみながら行うことが大切ですから、犬の気持ちを逆撫でするような事態は避けた方がよいのです。
もし簡単に犬の口をこじ開けることができないのであれば、もう1つボールを隠しておき、それを犬の近くに投げてやります。 すると引っ張りっこをしていても犬は新しいボールに興味を引かれますから、くわえていたボールを放して新しいボールを取ろうとします。
ここで犬がくわえていたボールを離す瞬間に「離せ」というコマンドを言います。 または、新しいボールのかわりに数粒のフードをばら撒く方法でも構いません。このときもタイミングよく「離せ」とコマンドを入れましょう。
新しいボールとフードをランダムに入れ替えながらしつけの練習をしていると、犬は「離せ」と言われたら口にくわえていたものを離すようになります。
しつけを終わる際は「おしまい!」と犬に合図を
このしつけで大事なことは、いつまでも離せのしつけの練習を行わないことです。犬がボールに飽きてしまい、ボールの価値が薄れていってしまうためです。
犬がボールに飽きると、他のしつけ方法を行う際にも、影響が出てしまうため、犬がボールに興味があるうちにやめておきましょう。大体7~8回程が限界です。
犬が飼い主とのやりとりやボールに魅力を感じていて「もう少し遊びたい」と思っているところで切り上げることが、数日間あるいは数か月間も繰り返してしつけの練習を続けて行くためのポイントです。
しつけは、あくまでも犬にとっては楽しい遊びなのです。
「離せ」が上手にできるようになってからも、散歩の帰り道にヒモつきボールを隠しておいてサプライズで引っ張りっこ遊びや「離せ」の練習をすることで頻繁に短時間のしつけを行うことができるのです。
また、離せのしつけを終える際は、犬を思い切り褒めたあとに、犬の身体をポンと叩き、「おしまい!」としつけの終わる合図をしてあげましょう。
この方法はほかのしつけにも応用でき、この方法で犬はしつけとのメリハリがつき、集中してボール遊びやしつけを行ってくれるはずです。
おわりに
しつけは1歳までが勝負だと多くの人が思っていますが、トイレトレーニング以外は成犬になってからでも可能です。
特にコマンドに従うことは、ある程度の集中力ができる成犬になってからの方が覚えが速いものです。
口にくわえた物を「離せ」という命令に従って離すことは拾い食い防止の観点からもぜひ覚えさせたいしつけです。
けれども、改まってしつけの時間を設けて厳しく教えるよりは、日常生活の中や散歩の帰り道で遊びながら練習した方が効果的です。
散歩の帰りというのは、犬がほどよく疲れているので興奮しすぎないので恰好のしつけタイムです。しつけタイムはさりげなく開始して、はっきりと「おしまい」と告げることでメリハリをつけることで終わるようにしましょう。
-

- 【2023年版】おすすめの犬映画20選!感動映画から笑える作品までご紹介!
- 犬好きの方のために映画を20本厳選しました。感動できる映画から笑える作品、ファミリー向けまで、犬の名作映画を邦画7本,洋画7本,アニメ6本を紹介します。それぞれの映画の魅力やあらすじを短い文章で簡潔に紹介しています。映画選びの参考にしていただければと思います。
- 犬と暮らしたい
-
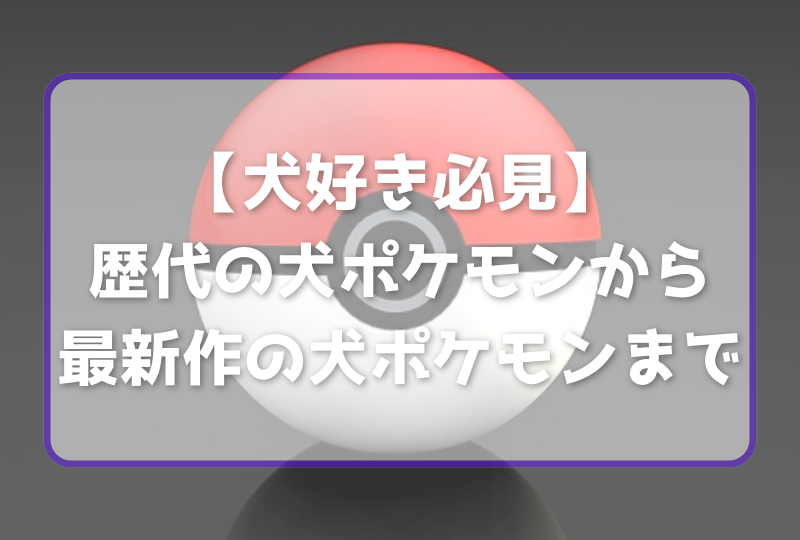
- 【犬好き必見】歴代の犬ポケモンランキング!最新作の犬ポケモンまとめてご紹介!
- 11月18日にポケモンシリーズ最新作「ポケットモンスタースカーレット」「ポケットモンスターバイオレット」が世界同時発売しました。そこで、今回は「歴代の犬ポケモン総まとめ」をお送りします。今までポケモンに興味がなかった方も、可愛くてかっこいい犬モチーフのポケモンにメロメロになっちゃうかも。
- 犬種図鑑
-

- 【獣医師監修】犬が口をくちゃくちゃする理由を解説!意外な理由と注意点を解説【2023年版】
- 犬が口をくちゃくちゃと動かしている様子を見たことがあるでしょうか。不思議な仕草なので、普段から気になっている飼い主さんも少なくないと思います。今回は口をくちゃくちゃする理由を紹介します。
- 犬の気持ち
-
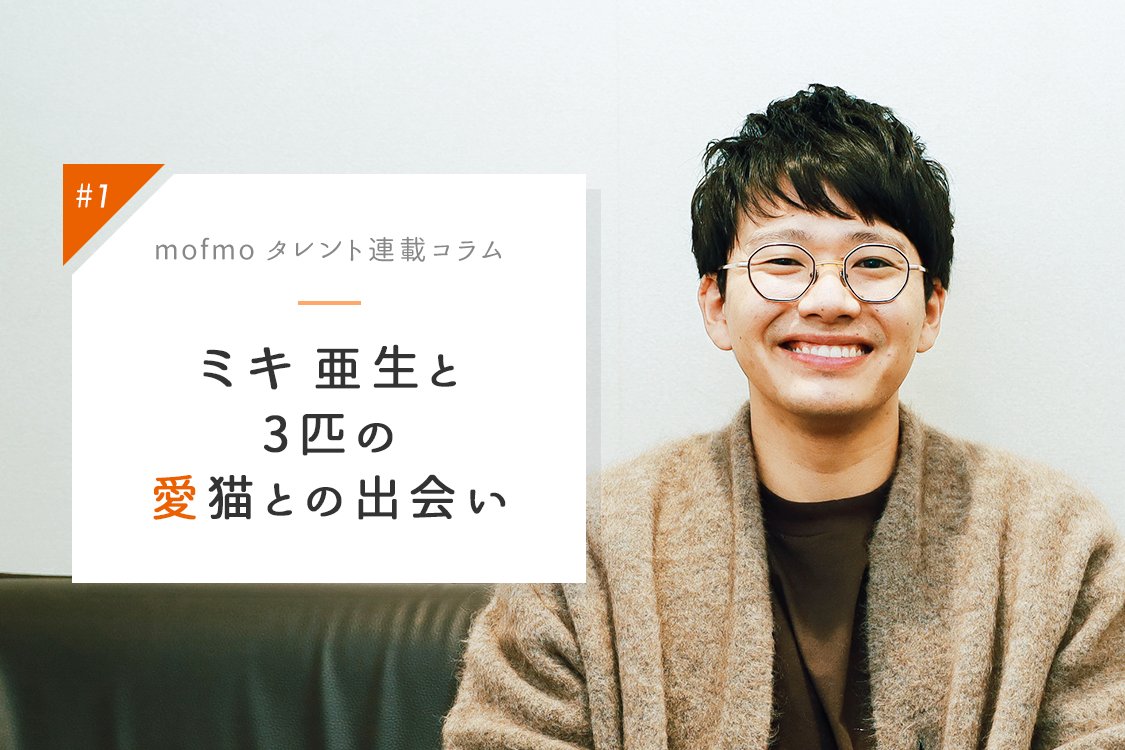
- ミキ亜生(芸人)/第1回 「犬派だった僕が、3匹も猫を飼うなんて夢にも思ってなかったです」
- お笑いコンビ・ミキの亜生さんは、自身が保護した3匹の猫ちゃん「助六(メス)」「銀次郎(オス)」「藤(メス)」と生活をしています。芸人として活躍する傍らで、街で見つけた猫を保護し、里親を見つける活動を行っている亜生さんに、保護猫活動や猫たちとの生活についてインタビューしました。
- お笑いタレント
-

- 【2023年版】犬が髪の毛を噛むのはなぜ?4つの理由とやめさせる方法を徹底解説!【ドッグトレーナー監修】
- 犬が女性の長い髪を噛みながら引っ張ったり、飼い主さんが寝ている時に髪の毛を噛んできたりすることがあります。飼い主さんにとってはちょっと困った行動です。犬は構って欲しくてこのような行動を取ります。今回は犬が髪の毛を噛んでくる時の気持ちと対処法をご紹介します。
- 犬のしつけ
-

- 【ドッグトレーナー監修】犬が目をそらす3つの理由!飼い主が嫌われている訳ではない?【2023年版】
- 愛犬と目が合うと嬉しい気持ちになりますよね。しかし、逆に目をそらされることはありませんか?なぜ犬は目をそらすのでしょう?もしかしてその人のことが嫌いなのでしょうか?犬が目をそらす理由を3つご説明いたします!
- 犬のしつけ
- コメント
うちの犬、私が見るといつも目をそらされるので嫌われているのかと思いました。 その反対だったのですね、、、 老衰でもう亡くなってしまいましたが…。
-

- 【ドッグトレーナー監修】こんなにたくさん!?犬の芸を定番から上級者向けまで紹介【2023年版】
- 愛犬に芸を教えたことはありますか? 犬が芸を覚えるのは、しつけのためもありますが、運動不足や老化防止にもいいものがあるんです。また、見た目がかわいいのでオススメものものありますね…! 犬の芸、今回は約40種をまとめて紹介します!
- 犬のしつけ
- コメント
おすわり・待て、しか、できません。
-

- 【ドッグトレーナー監修】犬が服を噛んでくる理由とは?犬の気持ちと対処法をご紹介【2023年版】
- 愛犬がパンツの裾や袖などを噛んで困る・・!」と悩んでいる飼い主さんは少なくありません。なぜ犬は人間の服を噛むのでしょうか?犬が飼い主さんの服を噛むとき、それはどんな気持ちや心理が隠されているのでしょうか?この記事では、犬が飼い主さんの服を噛むときの気持ちとその対処法について解説していきます。
- 犬のしつけ
- コメント
職場の飼い犬にいつも服を噛まれてしまうのですが、遊んでほしかったり、退屈しているのですね。私が笑いながら相手するので遊んでると思ってるかもしれません。対処法としては声を出して同調せず、犬が服を放すほどの音を出したりて服を放させ、静かに背を向けてみます。今日は思いっきり服に穴が空いてしまいました(泣)対処法が分かり、感謝申し上げます。
-

- 【2023年版】犬は落ち葉を食べてしまう原因とは?食べさせないための対策を解説!
- 犬の中には、落ち葉を食べる子がいるようです。風にあおられて動く落ち葉を追いかけて、そのまま食べてしまうのです。犬が落ち葉を食べてしまうのは何故でしょうか。今回は犬と落ち葉との関係について調べてみました。
- 犬のしつけ
mofmo掲示板
-

- 皆さんは、ペットが万が一脱走した場合の対策などありますか?
- 犬を飼って1年経ちました。トイプードルです。 我が子のように可愛いです。迷子になったらどうしようと、ふと考えてしまい 皆さんは、迷子になった際の対策、ならないようにする対策などあるのでしょうか?
- コメント
入り口にゲートを付けていることと、首輪に住所や連絡先を書いていますね。まぁマンションなので脱走しても同じ階のフロアをうろうろするくらいなんでしょうけど。
-

- 犬の歯磨きはどうしたらいい?
- ペットの歯を磨いてあげたいです。
- コメント
歯磨き代わりになるおもちゃを与えるのもいいと思います。きちんと磨いてあげることも大事だけど、らくするのも手だと思います。
-

- 犬を電車に乗せる時に気をつけること
- 電車に乗って病院まで行くことになりました。
- コメント
1番さんが言ってるようにキャリーバッグは絶対です。おとなしい子でも抱っこで乗るっていうのはダメですよ。たぶん電車の規約的にもダメだし、犬が苦手な方やアレルギーのある方、喘息の方など色々な方が乗るので迷惑になります。