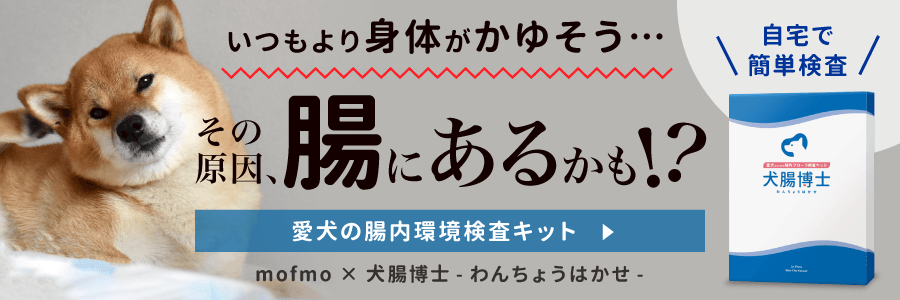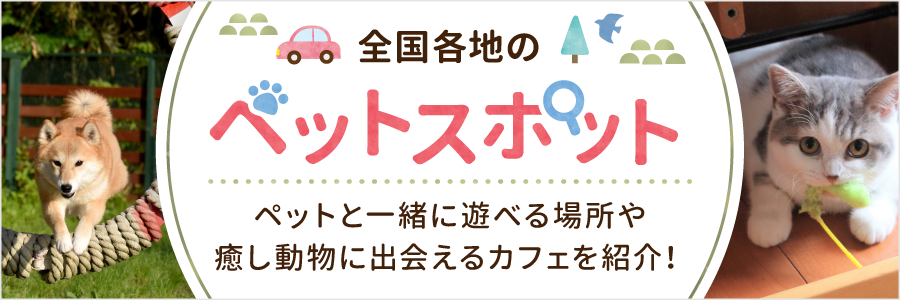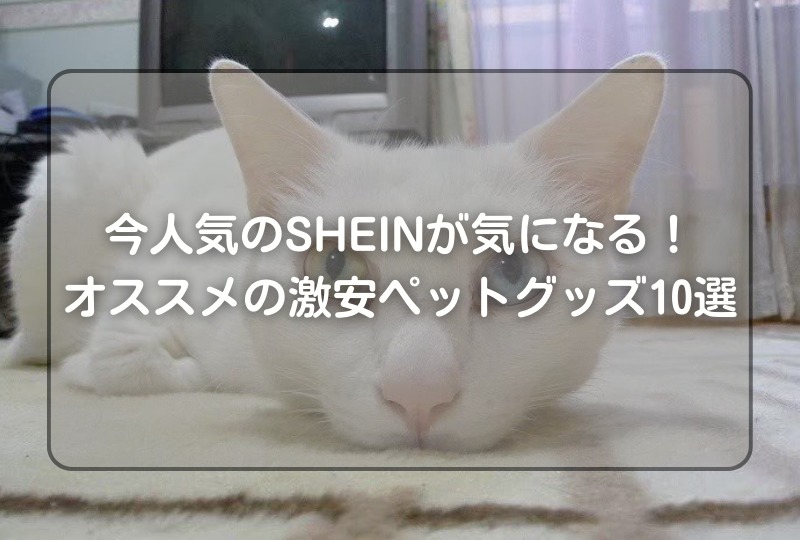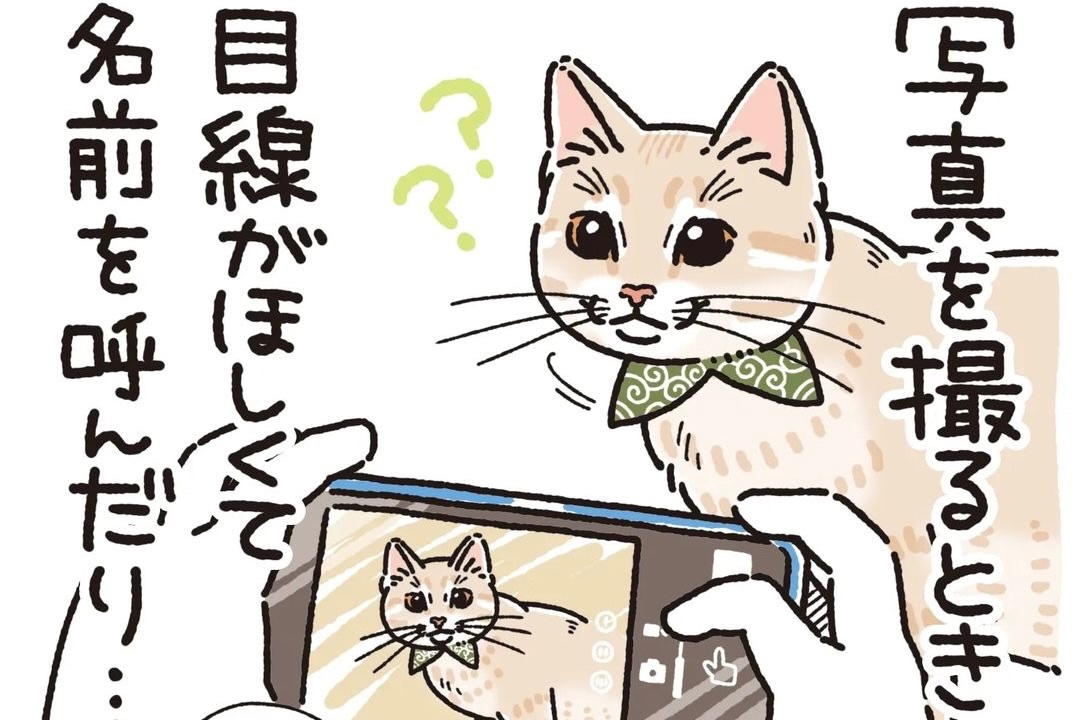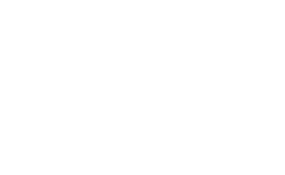【2023年版】犬は落ち葉を食べてしまう原因とは?食べさせないための対策を解説!
犬の中には、落ち葉を食べる子がいるようです。風にあおられて動く落ち葉を追いかけて、そのまま食べてしまうのです。犬が落ち葉を食べてしまうのは何故でしょうか。今回は犬と落ち葉との関係について調べてみました。

犬は落ち葉を食べることがある

Inna Dodor/shutterstock.com
犬の散歩中に、何かを口にしてしまうことは珍しくないでしょう。食べ物や普段見ないものなどを目にすると、それに興味をひかれて近寄ることは多いのではないでしょうか。中には落ち葉を食べる子もいるようです。風にあおられて動く落ち葉を追いかけて、そのまま食べてしまうのです。今回は、犬が落ち葉を食べてしまう原因と対策について詳しく考えていきたいと思います。
まずは、犬が落ち葉を食べてしまう原因について考えましょう!
犬が落ち葉を食べてしまう原因
どうして犬は落ち葉を食べてしまうのでしょうか?人間の私たちから見ると、枯れた落ち葉よりも道端に生えているみずみずしい草の方が犬には美味しそうにみえてますよね。
犬が落ち葉を食べる理由は、厳密に言えば分かっていない部分が多いようです。しかし考えられている理由のいくつかをあげていきます。
・「食感が面白い」 みずみずしい葉っぱとは違い、落ち葉は踏んだり噛んだりするとカサカサとした音や食感を味わえます。その音が面白く、遊びの感覚で食べてしまっているという場合もあり得ます。この場合には、食感や音が癖になり、たくさん食べ過ぎてしまうという危険もありますので、注意が必要でしょう。
・「胃の内容物を吐き出したい」 何かを誤飲してしまった時などに、それを吐き出したい、または胃の中にあるものを吐いてスッキリしたいときに、自分からわざと落ち葉をたくさん食べて吐き戻すという可能性も考えられているようです。
・「ストレスがある」 何かに対してストレス、不安などがある時には、気持を紛らわす為に異食に走り、落ち葉を口にするということがあり得ます。
・「異食症」 落ち葉以外にも、オモチャや小石、砂などの食べ物ではない物を口に入れてしまう時には、異食症になっている可能性もあります。すぐにかかりつけの病院に行き相談しましょう。
このように、落ち葉を口にする理由をいくつか考えることが出来ました。しかし、多少の落ち葉ならば構わないのでは?と考える飼い主さんも居ることでしょう。
次に、落ち葉を食べてしまう危険性について考えてみます。
犬が落ち葉を食べるリスク
落ち葉ですから、少量であれば特に気にする必要はないかもしれません。しかし、どのようなリスクがあるのかは把握しておく必要があるでしょう。
・「腸閉塞の危険」 少量の落ち葉であれば、排便の時に一緒に排出されるため問題はないでしょう。また、吐き出している場合であれば問題はないです。危険な場合は、大量の落ち葉を食べてしまった時です。あまりに大量の落ち葉を食べてしまうと、腸閉塞を起こしてしまう可能性があり得ます。
腸閉塞というのは、腸が完全に塞がれてしまっている状態、または腸の内容物が詰まってしまい深刻な通過障害を起こしている状態のことをいいます。症状としては、食欲不振、嘔吐、腹痛、便秘、下痢、元気がないなどです。
通過障害であれば、食欲不振、嘔吐、便秘や下痢などの症状が見られ、長引くと体重が減っていきます。完全な閉塞を起こしていたり、腸の粘膜が損傷していたりすると、腸内細菌の毒素が体内に入ってしまい、ショック状態になることもあります。
腸閉塞になってしまうと、投薬などで治療が行なえることもありますが、大抵の場合には開腹手術をして治す必要があります。
・「細菌や寄生虫の危険」 有毒な葉っぱを除けば、落ち葉に有毒な成分は特にはありません。しかし、落ち葉の表面に細菌や寄生虫が付着している可能性はあります。落ち葉と一緒に、そのような細菌や寄生虫を食べてしまうと、感染症になってしまうこともありますので、注意が必要です。
・「薬剤による被害」 公園などで管理されている木の場合には、農薬、殺虫剤などの薬剤が散布されていることもあります。その葉っぱが落ち葉になったら、薬剤の成分が残っている可能性もあります。少量の薬剤の摂取であればそれほど気にしなくていいかもしれませんが、体内にはなるべく取り入れて欲しくはないですね。落ち葉を大量に食べてしまう子であれば、その薬剤が体内に蓄積されていき健康被害を及ぼすということもあるでしょう。
・「有毒植物の被害」 普通の枯れ葉ならいいのですが、これが有毒植物の枯れ葉であれば注意が必要です。例えば、ツツジ科であるアザレアという植物は通年生えていて、その葉っぱには犬にとって有害な成分を含みます。ツツジ科は有害成分を含むものが多い為、注意しましょう。
他にもキンポウゲ科のクリスマスローズの葉っぱには、腹痛、下痢、不整脈、血圧低下、最悪の場合には心臓麻痺などを起こす可能性があります。ヒガンバナにも注意しましょう。田んぼや道端によく生えているものですが、皮膚に接触するだけで皮膚のかぶれを起こす可能性もあります。食べてしまうと、嘔吐や下痢、神経麻痺を起こします。また、ポインセチアもよく庭などで見ることもあるでしょう。最近では、品種改良も行われているので、一見ポインセチアとは分からないような植物もあります。イチジクの葉っぱに触れてしまうと、皮膚のシミ、粘膜のびらんなどの症状が現れます。スズランの葉っぱには猛毒で、心不全などを起こす作用がありますので、気をつけましょう。
他にも、まだたくさん危険なものはありますが、一つずつ取り上げることは不可能ですので、犬との散歩コースにどんな種類の草花が生えているか観察し、それが犬にとって危険のない植物かどうかを調べてあげてくださいね。
では、次に、落ち葉を食べさせない為に何ができるのかを考えていきましょう。
落ち葉を食べさせない為には?

Javier Brosch/shutterstock.com
落ち葉を食べさせない為には、落ちている物を拾い食いしないように躾けていく必要があります。拾い食いの癖がついてしまっている犬は、この機会にその癖を直せるように訓練しましょう。
どのように訓練できるのかをまとめてみました。
基本準備
まず、実際の拾い食いの躾の訓練に入る前に、犬が集中できる環境を作りましょう。私たちも同じですが、何か新しいことを覚えるには集中力が必要となります。そのため躾の前には、窓を閉じたり、テレビやラジオ、音楽などを消して他からの音を遮断します。気が散るようなオモチャなども片付けましょう。犬が飼い主さんのほうに向き合えるような環境を作ります。
犬の集中力は大体10分から20分程と言われています。集中力がなくなったなと感じたら、中断してまだ別の機会に行ないましょう。そのまま続けても犬にとって苦痛にしかならず、躾を覚えてくれないということになります。
拾い食いの躾は低質なオヤツ、上質なオヤツの2種類を準備します。日頃から犬をよく観察し、どんなオヤツが好きなのか見分けておきましょう。ご褒美にオヤツをあげる必要がありますので、カロリーの少なめの物を選ぶようにします。
拾い食いの躾をする前に、首輪とリードにあらかじめ慣らしておきましょう。拾い食いの躾は、床に落ちたオヤツに向かう犬を止める必要があります。叩いたり押さえ込んだりするのではなく、首輪やリードを引っ張ることで止めるようにします。その場合も、犬の大きさに合わせてストレスのない物を選びましょう。
準備は整いました!では、拾い食いをさせない為のしつけを始めていきましょう。
拾い食いをさせないための訓練
まずは、道に何かが落ちているという設定で部屋の中を再現します。床や部屋を綺麗にして、犬から見てすぐに分かるような場所にオヤツを落としておきます。犬のリードを短めに持って、その部屋の中を散歩しているかのように誘導していきます。
犬はオヤツの匂いを嗅ぎつけて、オヤツに近づいていくはずです。その時に飼い主さんは、犬が拾い食いをしないようにリードをしっかり持っておきます。ただし、注意点としては拾い食いをしそうな時に、大きな声を出して叱ったり、リードを首が閉まってしまうくらい強く引っ張らないようにしましょう。
リードに邪魔をされて、オヤツまで届かないと分かれば、そのうちに諦めます。諦めて飼い主さんのところへ戻ってきたタイミングで褒めてあげてご褒美のオヤツをあげましょう。この時のご褒美は、床にあるオヤツよりも良いもの、犬が大好きなものをあげてください。そのようにすることで、床に落ちている物の匂いを嗅ぐのを諦めて飼い主さんのところへ戻るなら、もっといいご褒美がもらえると覚えるようになっていきます。
使用する言葉を選択する
次に、諦めることと飼い主さんが指示する言葉をリンクさせていきます。犬がオヤツを諦めて飼い主さんのところに行くといいことがあると覚えたら、次のステップに移ります。オヤツに手が届かないと気付いて諦めた瞬間を見極めて、事前に決めておいた指示語を言います。
例えば英語の「放っておく」というリーブイット( Leave it)や、「触ってはいけない」のノータッチ(No touch)またはドンタッチ(Don’t touch)などです。ただ、ダメ!という言葉でもいいのですが、生活上の他の場面でも使っているはずですから、他の状況や言葉と混ざらないように英語や他の言語で言ってもいいでしょう。
ここで重要なのは、言葉をかける瞬間は、床に落ちている物から鼻先を離し、興味が薄れた瞬間である必要があります。その後に、思いっきり褒めてあげて、オヤツを与えれば、指示語=いいことがあると思わせることができるようになります。
この行動に少しずつ慣れてきたら、今度はリード無しでやってみましょう。リードがあった時と同じように、床の上にオヤツを落としておきます。もちろん、犬はオヤツに近づいていくことでしょう。鼻先をオヤツにつける瞬間を狙って、先程決めた指示語を言います。
-

- 【2023年版】おすすめの犬映画20選!感動映画から笑える作品までご紹介!
- 犬好きの方のために映画を20本厳選しました。感動できる映画から笑える作品、ファミリー向けまで、犬の名作映画を邦画7本,洋画7本,アニメ6本を紹介します。それぞれの映画の魅力やあらすじを短い文章で簡潔に紹介しています。映画選びの参考にしていただければと思います。
- 犬と暮らしたい
-
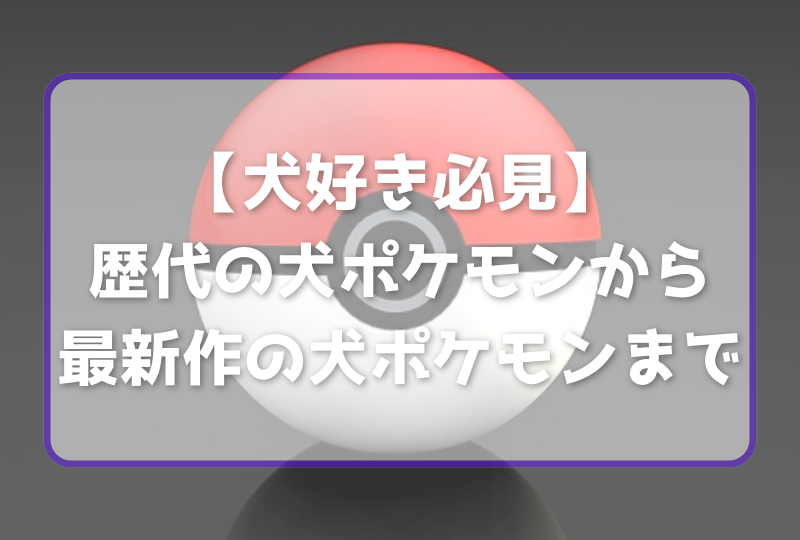
- 【犬好き必見】歴代の犬ポケモンランキング!最新作の犬ポケモンまとめてご紹介!
- 11月18日にポケモンシリーズ最新作「ポケットモンスタースカーレット」「ポケットモンスターバイオレット」が世界同時発売しました。そこで、今回は「歴代の犬ポケモン総まとめ」をお送りします。今までポケモンに興味がなかった方も、可愛くてかっこいい犬モチーフのポケモンにメロメロになっちゃうかも。
- 犬種図鑑
-

- 【獣医師監修】犬が口をくちゃくちゃする理由を解説!意外な理由と注意点を解説【2023年版】
- 犬が口をくちゃくちゃと動かしている様子を見たことがあるでしょうか。不思議な仕草なので、普段から気になっている飼い主さんも少なくないと思います。今回は口をくちゃくちゃする理由を紹介します。
- 犬の気持ち
-

- ペット同伴できる会社がある!?『ペットフレンドリーオフィス』があるマース ジャパンに行ってきた!
- 「カルカン」「シーバ」等のペットフードや「スニッカーズ」「M&M'S」のお菓子でも知られているマース インコーポレイテッド。日本の拠点であるマース ジャパンでは「ペットフレンドリーオフィス」というペット同伴出社が可能な制度があるんです。
- 犬と暮らしたい
-

- 【2023年版】徳島県のワンコと入れるドッグラン付きのSAPA一覧をご紹介!
- 愛犬と一緒に楽しめる徳島県内のドッグラン付きサービスエリアを紹介しています。ドライブ中に立ち寄るのにピッタリのサービスエリアなので、ちょっと寄り道してワンちゃんと一緒にランチタイムを楽しみましょう。
- 犬のお出かけ
-

- 【2023年版】佐賀県の犬と入れるドッグカフェ・レストラン一覧をご紹介!
- ワンちゃん用ランチやケーキを豊富に提供する佐賀県のドッグカフェを紹介しています。愛犬とのドライブ中に、旅行のついでに立ち寄って、愛犬同伴でランチを楽しんだりドッグランで思いっきり遊んだりしましょう!
- 犬のお出かけ
-

- 【2023年版】佐賀県のワンコと入れるドッグラン付きのSAPA一覧をご紹介!
- 24時間利用可能な自然公園も併設されたドッグラン付きサービスエリアがある佐賀県。休日には愛犬と一緒にドッグランで思いっきり遊んで、美味しい地元の海産物を使った料理を味わいましょう!
- 犬のお出かけ
-

- 【2023年版】島根県の犬と入れるドッグラン付きの道の駅をご紹介!
- 島根県にあるドッグラン付きの道の駅をご紹介します。ワンコと一緒にのんびりと旅を満喫するのにおススメのスポットですよ!
- 犬のお出かけ
-

- 【2023年版】鹿児島県のワンコと入れるドッグラン付きのSAPA一覧をご紹介!
- ワンちゃんと一緒に楽しめる鹿児島県のドッグラン付きサービスエリアを紹介しています。雄大な桜島を眺められる展望台や、地元鹿児島県産黒豚を使用したランチは必見です。
- 犬のお出かけ
mofmo掲示板
-

- 留守番時に吠え訴えている愛犬
- 私が仕事に出かかえようとすると、吠えて飛びかかり阻止してきます。ゲージに入れて留守番させたほうがいいのか悩んでいます。
-

- 我が家のうさぎと新幹線で帰省を検討中!
- 新幹線で我が家のうさぎと一緒に帰省しようと考えています。 ペットと新幹線にのったことがないので、新幹線での注意したほうがいいことありますか?
- コメント
稀にキャリーケースの中では「排泄をしない」「飲食をしない」っていう個性の子もいるから先にキャリーに入れて長時間様子を見るといいかも。あとは指定席でペットを置く座席を予約しておくのもおすすめだけど会社によって違うので実際使うところの鉄道会社に問い合わせてみて!
-

- 皆さんは、ペットが万が一脱走した場合の対策などありますか?
- 犬を飼って1年経ちました。トイプードルです。 我が子のように可愛いです。迷子になったらどうしようと、ふと考えてしまい 皆さんは、迷子になった際の対策、ならないようにする対策などあるのでしょうか?
- コメント
入り口にゲートを付けていることと、首輪に住所や連絡先を書いていますね。まぁマンションなので脱走しても同じ階のフロアをうろうろするくらいなんでしょうけど。