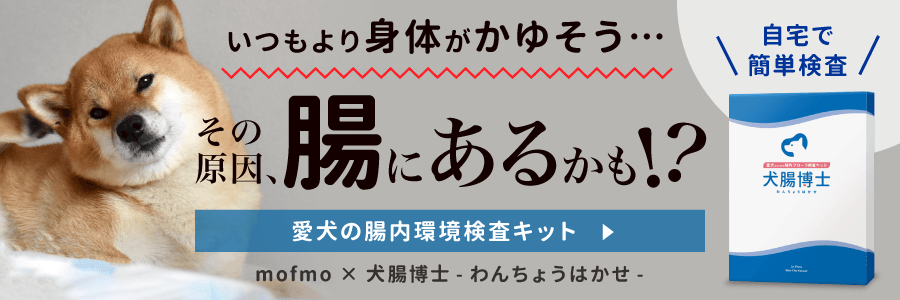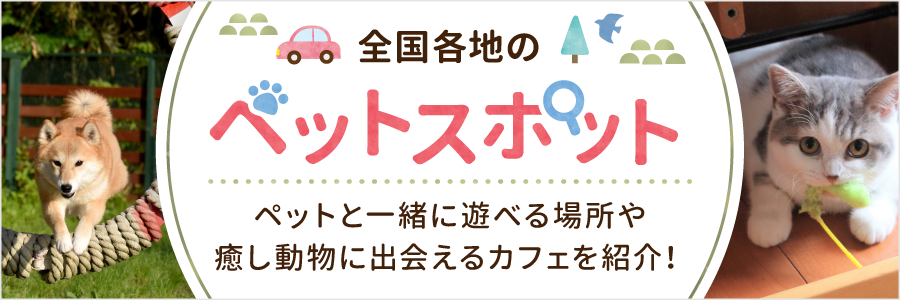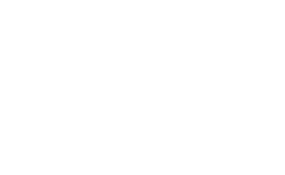猫が脱走したらどう対処すべき!?猫の行動範囲を知って正しい対策を講じよう
猫は時折脱走してしまうことがあります。脱走されると心配になってしまいますが、大事なのは冷静に対処することです。この記事では猫の行動範囲について解説するとともに、猫が脱走した場合に飼い主が行うことのできる対処法を紹介します。

愛猫が脱走したときに行うべきこととは?

AP Group of Photographers/shutterstock.com
では何かしらの理由で愛猫が脱走してしまった時、飼い主さんはどのように対処できるでしょうか?次の対処法を行いましょう。
対処法1.自宅付近を捜索すること
上記でもみたように、猫の行動範囲はそれほど広いものではありません。特に飼い猫の場合は万が一脱走したとしても、自宅の半径500メートル前後に潜んでいるケースが多いです。
家の軒下などに動かずにずっとしていることも珍しくありません。もし愛猫が外に脱走してしまったら、洗濯ネットにフードを入れて、まずは自宅付近を捜索しましょう。
猫は嗅覚がとても優れているので、洗濯ネットから漂うフードのにおいをキャッチし、フラっと姿をあらわすかもしれません。
そして、猫を見付けた場合は、すぐに洗濯ネットに入れて保護することができます。注意したいのは、愛猫を見付けると、つい嬉しさのあまり捕まえようとして追ってしまいがちですが、猫は追うとたいてい逃げます。
ですから、お気に入りのフードで操り、猫の方から近付いてくるまで待つようにしましょう。そして、捜索場所は自宅付近を中心に行うことがポイントです。猫は隠れることが上手な動物ですので、一度探した場所でも時間を変えて何度も探すようにしましょう。
また、猫が好む狭くて暗い場所も忘れずに確認するようにしましょう。愛猫を捜索するときは、おそらく多くの飼い主さんが猫の名前を呼ぶことでしょう。
名前を呼ぶ時はいつもの調子で呼ぶことが大切です。もし大声で呼ぶなど、いつもと違う様子だと警戒してしまい近くにいても出てこなくなってしまうこともあるので、呼び方にも注意しましょう。
対処法2.自宅の窓やドアを少し開けておくこと
家の防犯には充分注意する必要がありますが、自宅の窓やドアを少し開けて、そこに愛猫が大好きなフードやおやつなどを入れたお皿を置いておくことも効果的です。
脱走しても、お腹が空いたら愛猫は何かを食べに戻ってくる可能性があります。また、特別なおやつならにおいを嗅覚で区別し、戻ってくるかもしれません。
対処法3.猫が脱走したことを保健所や警察などの連絡しておくこと
猫が脱走した場合、連絡すべき場所はいくつかあります。それには保健所、動物管理事務所(動物愛護センター)、清掃事務所(クリーンセンター)、警察署、そして、動物病院です。
連絡する際には、
「○月○日(逃げた日)から、飼い猫が行方不明になっています。○○付近(住んでいる地域名)で、猫は○○(猫種や色などの特徴)をしています。保護や引き取りなどはありましたか?」
と確認してみましょう。
〇保健所 保健所には、保健所が保護した猫に加え、保護してくれている人からの保護情報が入っていることもあります。
〇動物管理事務所(動物愛護センター) 動物管理事務所には、3日おきくらいの頻度で確認をしてみることができるかもしれません。
〇清掃事務所(クリーンセンター) 清掃事務所は、交通事故に合った動物を引き取る場所です。飼い主さんにとっては考えたくない最悪なケースですが、勇気を出して確認してみましょう。
〇動物病院 動物病院にも、保護された猫が運び込まれている可能性があります。自宅近くの動物病院すべてを確認してみることができるでしょう。
対処法4.SNSなどインターネットを使って情報を共有すること
愛猫が脱走したら、SNSや迷子掲示板などインターネットを活用し、情報提供を求める投稿もしてみることも効果的です。
愛猫を見つけるために使える手段は全て使うという意気込みでたくさん投稿し、愛猫を見つける手がかり探しましょう。
対処法5.猫の迷子チラシを作成し貼ること
猫の写真や特徴、連絡先などを記載してチラシを作って、多くの人の目に触れる場所に貼ることができます。その際、チラシに「発見につながる情報を提供してくださった方には、気持ちですが謝礼を差し上げます」などの文章を一言加えるとさらに効果がアップするでしょう。
近所はもちろん、動物病院などにも貼らせて貰えるようお願いしてみましょう。
チラシのサイズはあまり大きいと場所を取るため断られる可能性もあるので、大きくても A4サイズくらいまでにしておくことがポイントです。
チラシの作成枚数は、住んでいる地域によって必要枚数は異なってきます。
脱走直後の場合は、自宅の50~100m位の範囲に配れる程度の枚数、脱走から1ヶ月以上経過している場合は、少し範囲を広げ1.5km位まで配れる程度の枚数を目安として用意することができるかもしれません。
自分でチラシを作成することもできますが、迷子ペット専門チラシ作成業者もいますので、依頼を検討してみることもひとつの方法です。
対処法6.ペット探偵に依頼する
どうしても愛猫が見つからない場合は、ペットを専門としているペット探偵に捜索を依頼することができるかもしれません。
少々高額ですが、愛猫を見つけるための最終手段として利用を検討してみることができるでしょう。
対処法7.愛猫が帰ってくるまで絶対に諦めないこと
もし飼い主さんが諦めてしまうと、見つかるべきものも見つからなくなってしまいます。ですから、「愛猫は絶対に見つかる!」という強い気持ちを持ち、探すことを絶対に諦めないようにしましょう。
まとめ
猫の行動範囲や脱走する理由、脱走した時の対処法などについてみてきましたが、いかがでしたか?
猫の行動範囲は、比較的狭いものです。愛猫が脱走してしまうと、ついつい不安でいっぱいになってしまい冷静さを失ってしまいますが、まずは落ち着いて自宅付近から探してみましょう。
そして、愛猫がなかなか戻って来なくても、決して諦めてはいけません。是非、上記でご紹介した対処法を実践されることをおすすめします。
-
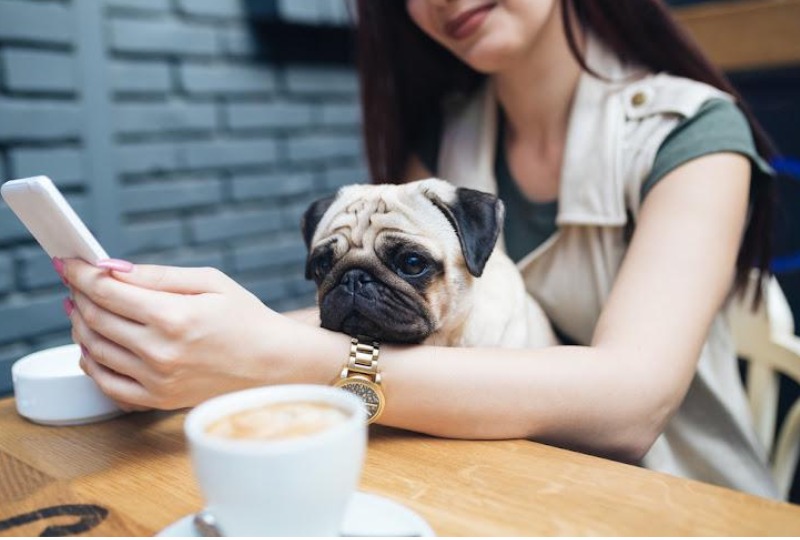
- 【2023年版】東京都内の犬と入れる人気ドッグカフェ一覧をご紹介!【63店舗】
- 愛犬と一緒に楽しめる東京都内のドッグカフェを紹介しています。わんことのお出かけ中、乗り換えのついでに立ち寄るのにピッタリのお店や、遠くからでもわざわざ訪れたくなる魅力的で新しいカフェで愛犬と一緒にまったり過ごしましょう!
- 犬のお出かけ
-
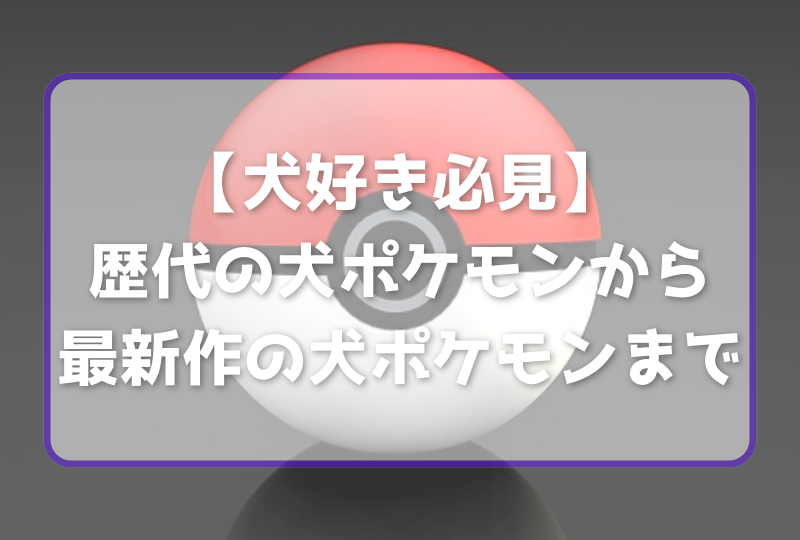
- 【犬好き必見】歴代の犬ポケモンランキング!最新作の犬ポケモンまとめてご紹介!
- 11月18日にポケモンシリーズ最新作「ポケットモンスタースカーレット」「ポケットモンスターバイオレット」が世界同時発売しました。そこで、今回は「歴代の犬ポケモン総まとめ」をお送りします。今までポケモンに興味がなかった方も、可愛くてかっこいい犬モチーフのポケモンにメロメロになっちゃうかも。
- 犬種図鑑
-
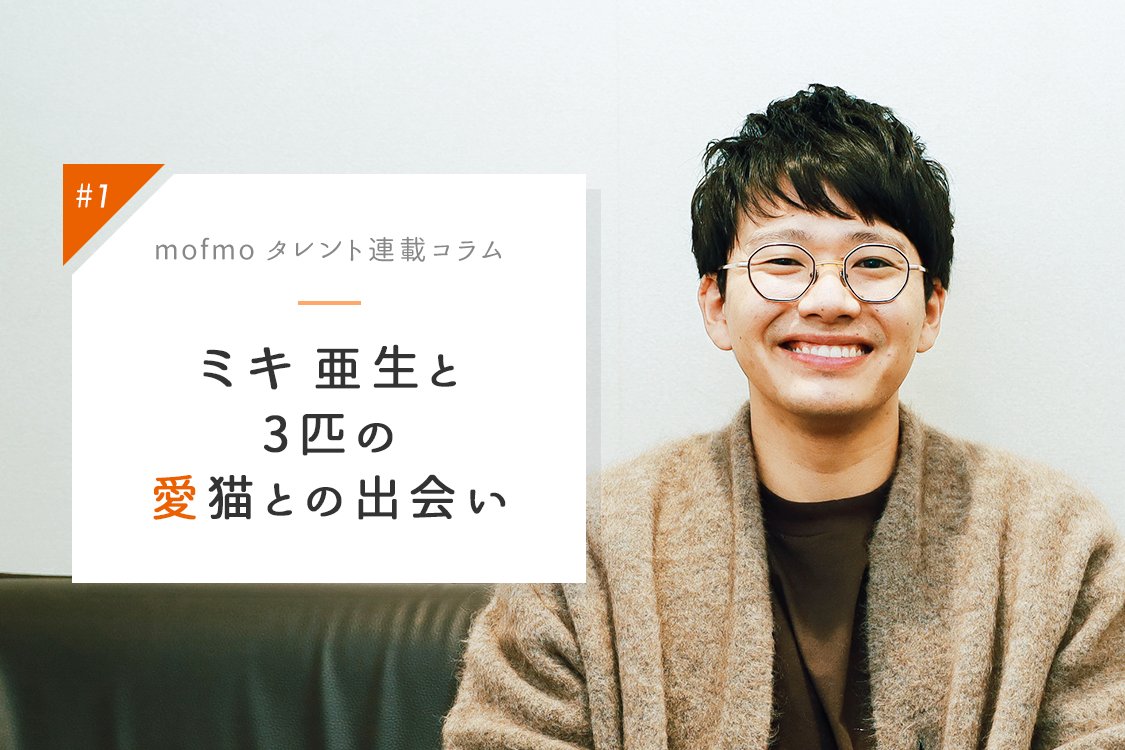
- ミキ亜生(芸人)/第1回 「犬派だった僕が、3匹も猫を飼うなんて夢にも思ってなかったです」
- お笑いコンビ・ミキの亜生さんは、自身が保護した3匹の猫ちゃん「助六(メス)」「銀次郎(オス)」「藤(メス)」と生活をしています。芸人として活躍する傍らで、街で見つけた猫を保護し、里親を見つける活動を行っている亜生さんに、保護猫活動や猫たちとの生活についてインタビューしました。
- お笑いタレント
-

- ペット同伴できる会社がある!?『ペットフレンドリーオフィス』があるマース ジャパンに行ってきた!
- 「カルカン」「シーバ」等のペットフードや「スニッカーズ」「M&M'S」のお菓子でも知られているマース インコーポレイテッド。日本の拠点であるマース ジャパンでは「ペットフレンドリーオフィス」というペット同伴出社が可能な制度があるんです。
- 犬と暮らしたい
-

- 【2023年版】猫を飼っている芸能人・有名人を男女別にご紹介!
- “猫好き”を公言している芸能人もたくさんいますよね。テレビを見ると、ニャンコを飼っている芸能人も意外に多い気がします。そこで今回この記事では、猫ちゃんを買っているジャニーズや芸能人を男女別に10選ずつご紹介します。かわいい愛猫の写真にほっこり癒されること間違いなしです♪
- 猫と暮らしたい
- コメント
1
-

- 【2023年版】夏にピッタリ?!話題のライオンカットとは?猫へのメリットと危険について解説
- 暑い時期が近づいてくると、暑さ対策が話題になりますよね。夏の時期が近づくと、愛猫の被毛を短くカットしたいと思うかもしれません。最近ではその一環でライオンカットというものが流行っています。ここではライオンカットの方法やメリット、さらにその危険性などについても扱いたいと思います。
- 猫のお手入れ
-

- 【獣医師監修】猫に菜の花はNG?猫草代わりとして与えてもダメ?注意点やリスクを解説【2023年版】
- 春になると鮮やかな黄色の花を咲かせる菜の花。独特のほろ苦さと香りが魅力なことから鑑賞以外に食用としても人気の菜の花ですが、猫が食べても大丈夫なのでしょうか?この記事では猫に菜の花を食べさせる場合にどんな点に気を付けたらいいのかを解説します。また猫草代わりに菜の花を与える際に注意したい点も説明します。
- 猫の食べ物
-

- 【獣医師監修】猫にレンコンを与えても大丈夫?含有している栄養素や猫へのメリットをご紹介!【2023年版】
- 小鉢料理などで活躍するレンコンは、日本人にとってなじみの深い野菜の一つです。栄養素も豊富なので、愛猫にも与えようかどうか迷っている人も多いでしょう。でもレンコンは野菜なので、肉食の猫には与えても大丈夫なのか心配な人も多いはず。そこで今回は猫とレンコンの相性について調べてみました。
- 猫の食べ物
-

- 【2023年版】猫がゴロゴロ・クネクネ転がるのはなぜ?!理由や猫の心理を解説
- 猫は警戒心の高い動物のはずなのに床でゴロゴロ転がっていたり、仰向けで爆睡したり、へそ天状態でクネクネしたり、急所であるはずのお腹を丸出しにしたりすることがあります。そんな猫の行動には、本能に基づく理由やその姿を見せている相手に伝えたい気持ちが込められています。ここではそんな猫の心理をご紹介します。
- 猫の気持ち
mofmo掲示板
-

- マルチーズを飼っていますが、涙焼けがひどくどうしたら除去できるのでしょうか?
- こまめに目の周りを拭いていますが、涙焼けがひどくなる一方です。
- コメント
うちの子はチワワですが、1、2才の頃まで涙焼けがひどかったです。ただドライフードを替えたり、出来るだけ手作りのご飯に替えたりしてみると、その後ずっと涙焼けしなくなりました。
-

- 真夏のお散歩の対策教えてください!仕事の関係上、お昼にしか散歩できません。
- 仕事の関係上、お昼にしか散歩に行く時間がとれません。 飼い始めたばかりですが、夏の散歩がこんなにも負担がかかるなんて、想像もしませんでした。 夏の散歩対策おしえてください!!うちの子は、フレンチブルックの生後6か月です。
- コメント
日の沈んだ夜に散歩できたら夜に散歩したり、休みの日の朝にすると良いのですが それが不可能なら、犬の為の靴を履かせて 散歩すると火傷は回避出来ると思います。
-

- 猫去勢費用。平均いくらですか?
- 里親になりました。子供の頃に猫をかっていましたが、20年ぶりに家族に迎え入れます。 去勢を考えていますが、平均どのくらいの費用と入院期間が必要なのでしょうか?
- コメント
うちの場合は去勢(オス)が1万7000円前後、不妊(メス)で2万8000円前後でした。体重によって5000円程前後します。それに、我が家は多頭飼いし始めだったため、年に何回かお願いしたので2匹目からは2000〜3000円程の割引がありました。 ただ、保護猫限定なのかは不明ですが、隣県の方から猫をもらった時、不妊手術の証明で領収証をもらいましたが、7000円でやってくれる病院もあるようです(ちなみにその猫さんはさくら耳ではありません)。 地域と保護猫かどうか、あとは病院によって違いがあるようです。