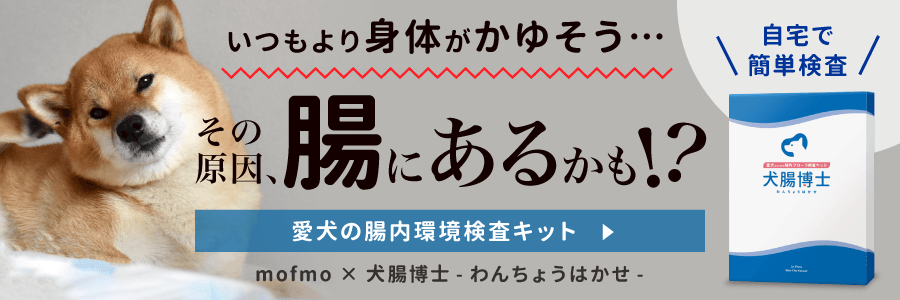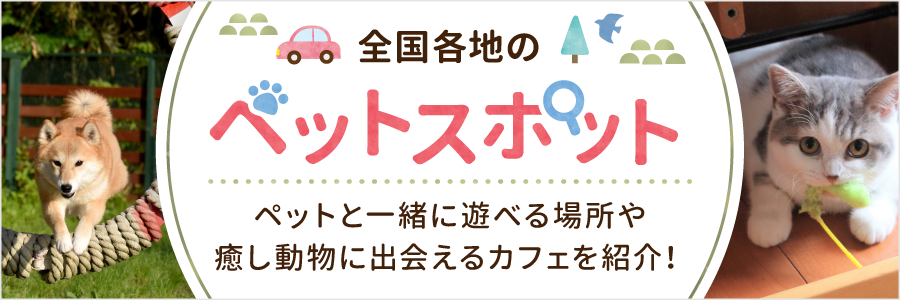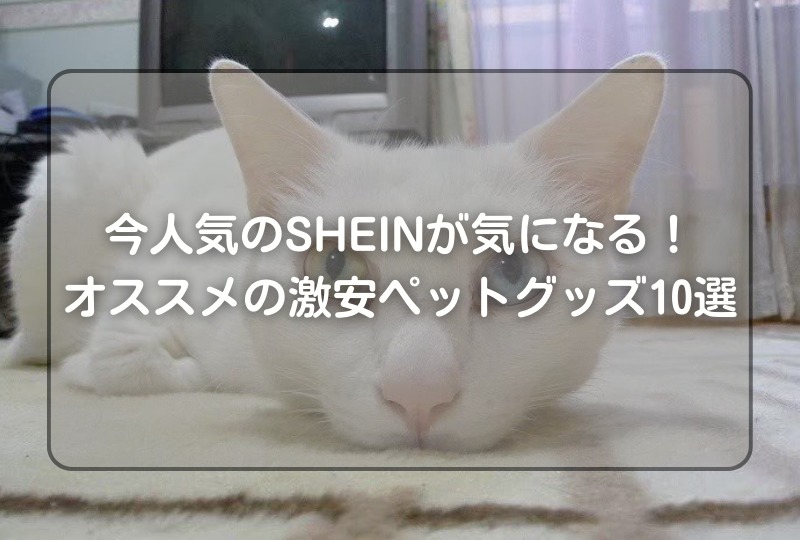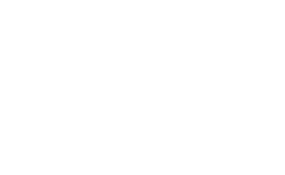犬の里親になる条件は厳しい?厳しすぎる理由についてもご説明
犬の里親募集はたくさんあります。これだけたくさん新しい飼い主を待っている犬がいるのなら、里親になることは簡単だと思ってしまいます。犬の里親になるのはいくつかの厳しい条件をクリアしなければなりません。厳しい条件とは何ですか?実情はどうですか?度が過ぎて厳しいですか?

■犬の里親になる条件は?

pixabay.com
里親募集の団体や保健所など犬の里親募集をしている機関は数多く存在していますが、それぞれの施設によって里親として保護している犬を譲渡するための条件は総合的に厳しいですが、機関や団体により異なります。しかしここでは、一般的な里親となる人の条件について取り上げます。 この先、飼い主のいない犬を増やさないために、譲渡する犬の避妊手術費用を負担して、犬の引き受け時にきちんと行うことができることは、多くの施設の要求条件となっています。犬の3種混合ワクチンや白血病予防ワクチンを接種できる方、犬を飼うことに関して同居者全員の総意を得られることと、生涯家族の一員として大切に最後まで世話することができること、持ち家もしくはペット同居可能な住宅に住んでいること、集合住宅や賃貸住宅の場合は、不動産や管理業者の飼育許可書が必要とする場合もあります。一日の在宅時間が短い場合は子犬の譲渡をお断りすることもあります。 乳幼児や近いうちに出産を控えている妊娠中の家族がいたり、また施設によっては小学生以下のお子様のいる家庭では子犬や小型犬の引き受けはできないことを条件としているところもあります。動物アレルギーの家族がいるなら、医師の診断書が必要です。一人暮らしの方、同棲中のカップル、もしくはご高齢の方は里親になれないことがあります。未成年者は同居の保護者が申し込むなら里親になることができます。生計が立てられる収入があることも条件となります。先住犬は避妊、去勢主手術が済んでいることが条件です。犬の正式な譲渡の前に2週間のトライアル期間が設けられ、トライアル期間開始の引き渡しの時に、居住環境を担当者に見せるなど厳しい条件が含まれていることもあります。 様々な条件を総合的に検討し、個々の犬の性格や適正も考慮した上で、里親になるための資格を満たしているかどうかを判断します。上記に挙げた条件以外にも里親となる人に対して、不当に厳しいと思えるような義務を要求する施設もあります。例えば、世帯主の源泉徴収票、または預金残高証明の提出が求められたり、勤務先の連絡先の申告(実際にそこへ電話して就労実態の確認をするため)、身分証明書類のコピーや不動産登記の提出、譲渡後には、毎週、犬の成長証明を報告することや、施設への寄付を求めたり、事前連絡あり、またはなしで自宅訪問や自宅調査など、ハードルが高すぎて厳しいため里親になるための応募を躊躇してしまいそうな条件があるケースもあります。
-

- 【2023年版】おすすめの犬映画20選!感動映画から笑える作品までご紹介!
- 犬好きの方のために映画を20本厳選しました。感動できる映画から笑える作品、ファミリー向けまで、犬の名作映画を邦画7本,洋画7本,アニメ6本を紹介します。それぞれの映画の魅力やあらすじを短い文章で簡潔に紹介しています。映画選びの参考にしていただければと思います。
- 犬と暮らしたい
-
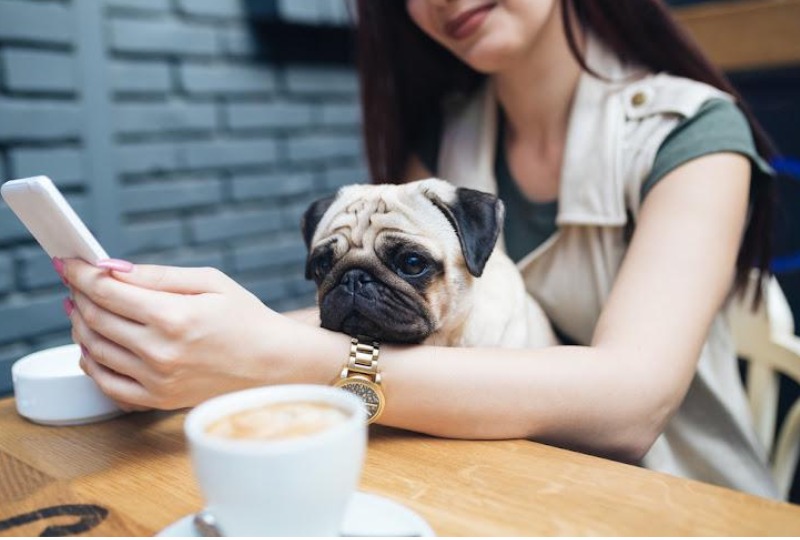
- 【2023年版】東京都内の犬と入れる人気ドッグカフェ一覧をご紹介!【63店舗】
- 愛犬と一緒に楽しめる東京都内のドッグカフェを紹介しています。わんことのお出かけ中、乗り換えのついでに立ち寄るのにピッタリのお店や、遠くからでもわざわざ訪れたくなる魅力的で新しいカフェで愛犬と一緒にまったり過ごしましょう!
- 犬のお出かけ
-
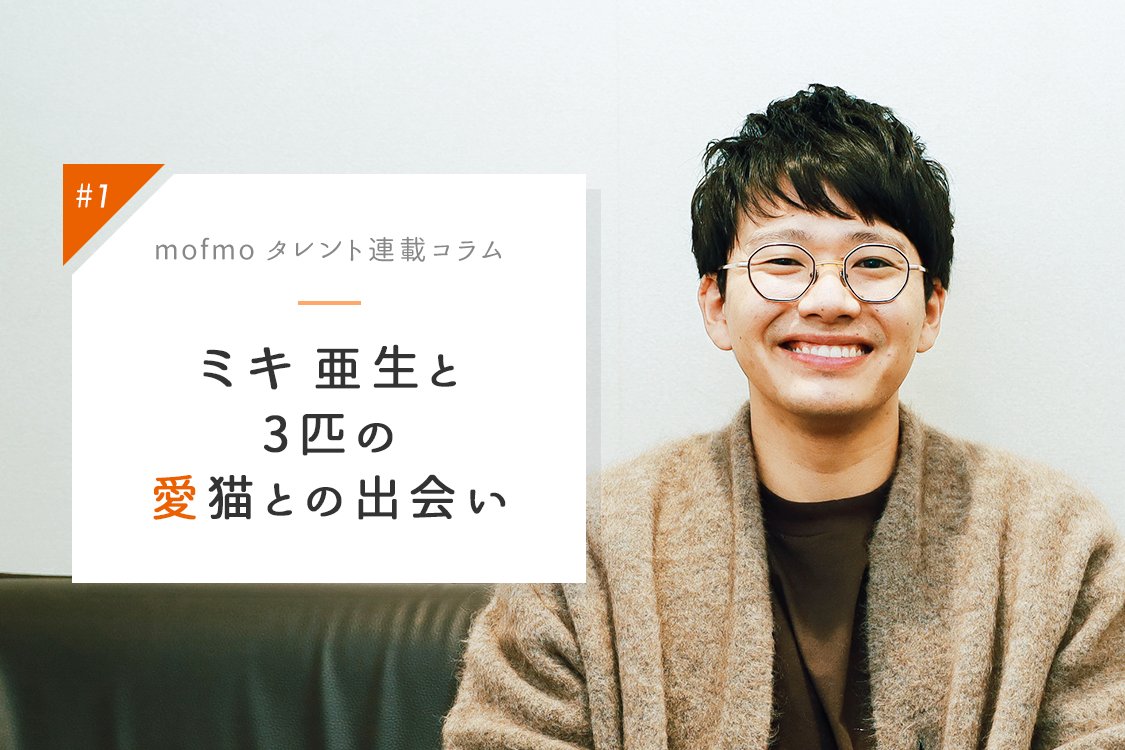
- ミキ亜生(芸人)/第1回 「犬派だった僕が、3匹も猫を飼うなんて夢にも思ってなかったです」
- お笑いコンビ・ミキの亜生さんは、自身が保護した3匹の猫ちゃん「助六(メス)」「銀次郎(オス)」「藤(メス)」と生活をしています。芸人として活躍する傍らで、街で見つけた猫を保護し、里親を見つける活動を行っている亜生さんに、保護猫活動や猫たちとの生活についてインタビューしました。
- お笑いタレント
-

- ペット同伴できる会社がある!?『ペットフレンドリーオフィス』があるマース ジャパンに行ってきた!
- 「カルカン」「シーバ」等のペットフードや「スニッカーズ」「M&M'S」のお菓子でも知られているマース インコーポレイテッド。日本の拠点であるマース ジャパンでは「ペットフレンドリーオフィス」というペット同伴出社が可能な制度があるんです。
- 犬と暮らしたい
-

- よく耳にする「保護犬」って具体的にどんな犬のこと?幸せになる犬を増やそう
- 最近では、犬を飼いたいと思ったら、ペットショップやブリーダーで探すのではなく、保護犬を選択肢に入れることが勧められていますが、保護犬についてよく知らないがゆえに、「なんだか複雑そう…」と敬遠してしまう人も多いようです。そこでこの記事では、保護犬とはどんな犬なのか、基礎知識をご紹介します。
- 犬と暮らしたい
-

- 最近話題の犬の預かりボランティアとは?活動内容とボランティアの魅力を紹介!
- 愛犬家の中には「犬のために何かしたい」「救える命があるのなら役に立ちたい」と考えている方が少なくなく、最近では保護犬を引き取る動きも見られるようになっています。一方で、ペットロスやその他の事情で「新しい犬を飼う気はまだしない」という方もいます。そんな方におすすめなのが「犬の預かりボランティア」です。
- 犬と暮らしたい
-

- 黒いフレンチブルドッグを飼いたい!値段やブリーダー・里親について
- フレンチブルドッグは、常に笑顔を振りまき、愛くるしい行動が人気の犬種です。フレンチブルドッグには、様々なカラーがありますが、その中でも黒いフレンチブルドッグは希少です。黒いフレンチブルドッグの値段や、里親の探し方、ブリーダーについてご紹介いたします!
- 犬と暮らしたい
- コメント
カラーの種類って結構ありますね。それぞれのカラーに名前が付いているのも初めて知りました。ハニーパイド、片パンチとかは印象的でした。それぞれの写真があったら、よかったなぁと思いましたが、希少なら写真も見つかりにくいのかもですね。
-

- アイリッシュセッターの子犬の価格はいくら?里親になる方法についても解説
- 見た目にも美しいアイリッシュ・セッターは鳥猟犬としてイングリッシュセッターと人気を二分してきました。引き締まった体に優雅に走る姿はなんとも言えない美しさです。ではそんなアイリッシュ・セッターを飼いたい時の価格や購入方法、里親になる方法を見てみましょう。
- 犬と暮らしたい
-

- アメリカン・コッカー・スパニエルの子犬の価格について。里親のなり方についても解説。
- ふんわりとした被毛とクリクリした目、長く垂れた耳が魅力的なアメリカン・コッカー・スパニエル。ディズニー映画「わんわん物語」のレディちゃんのモデルになった犬種としても有名です。そんな愛らしいアメリカン・コッカー・スパニエルを飼いたいという方に、子犬の価格や里親のなり方についてお教えします。
- 犬と暮らしたい
- コメント
メリーコッカーっていう愛称が付けられてるほど、陽気な性格ってそういうのいいね。明るい性格の子と一緒にいたら、こっちまでどんどん明るくなれてしまうかも。悩みも、深刻には思えないようにもなりそうな予感が。
mofmo掲示板
-

- 多頭飼いしたい。けど家族には1匹で十分だと言われます。
- 多頭飼いしたきっかけ、教えてください!
- コメント
もう1匹犬を飼いたいですが、家族に反対されます
-

- 先住の猫と新しく迎える猫の相性
- 自宅にいる猫と、実家にいる猫が一緒に住むことになった場合 お互いの猫に配慮することはありますか? 実家では猫を飼うことが難しくなったので、引きとる方向で話が進んでいます。
- コメント
まず引き取ったら、ゲージの中に入れて先住猫にあわせないまま数日過ごさせましょう。先住猫に存在を知らせることで、面会までに心の準備をさせてあげましょう。その後面会させるときは、慣れるまではお互いゲージ越しのほうがいいと思う。最初が大事なので、じっくりじっくり慣らさないとだめです。
-

- 今度ドックランデビューします!マナーをおしえてください!
- ドックラン特有のマナーってありますか?飼い主のわたしが、緊張してます。
- コメント
マナー?自由奔放に走り回らないように周囲の邪魔にならなければいいと思いますよ。証明書とかはもちろん必要ですけど、それはマナーとは違いますよね
条件が厳し過ぎると、せっかくのチャンスを逃してしまう子多いと思う。
けど、返却や、再度見捨てられるケースも多く、厳しいのも分かる。
中でも、理解出来ない条件で、飼育経験がない→ペットショップで購入しないと生涯里親無理
子供がいる→飼育チャンスがないから生涯里親にはなれない
留守が少ない→クリアできていても、専業主婦、高齢者、子供がいる家庭か自営業。
中でクリアできるのは子供がいない自営業。少子化増える。
こういう家族構成はダメとか、触れあう時間をしっかり取れるとか、条件を少し広げては。
条件があるなら、なぜこのような条件があるのか等、理解が得られる説明をして欲しい。
そもそも保護犬は条件があって、ペットショップの場合は条件がないというのもおかしいですよね。
厳しすぎても里親が増えないですし、、
ペットを飼う行為そのものが、飼い主の責任感を意識させるように、規制やら、教育が行き届いていくといいですねぇ。。
そもそも里親になる事と犬を飼う事を一緒に考えてはいけないと思います。
普通に犬を飼いたいならペットショップやブリーダーからで良いと思います。
可哀想な保護犬を減らしたい、社会に貢献したいと思う方は里親に。
保護犬を飼う時のリスクはかなりあります。
一般の家でペットとして飼われていた犬を譲り受けたなら当たりですが、
野犬、多頭飼い崩壊、飼育放棄、虐待からの保護犬は健康面や精神面でも問題が多く、しつけの入っていない状態が殆どです。
病歴も分からず一から診察して治療してしつけをするとなれば、人手もお金もかかります。
だったらお金を払ってでも今現在健康で、その子の持つ病気の因子や特徴がある程度分かっているペットショップやブリーダーから迎えた方が飼い主としてもリスクは少ないと思います。
私は里親にもなった事がありますが、ペットを飼うなら里親になる選択肢もというのには疑問がわきます。
里親になるには可哀想な保護犬を一匹でもなくしたいという人でなければ心や健康面で問題を抱えた犬は難しく、厳しい里親条件や自宅訪問はさらに保護犬の引き取り手を無くすはずです。
幼犬から育てるペットとの生活と保護犬の里親になる事は別物だと思います。
ペットショップから犬を迎える事を悪く言う保護団体の方も居ますが、
私はそれも人それぞれだと思います。
世の中の捨て犬の保護や治療よりも、まず自分の愛犬にお金と時間をかけたいと思っても良いんじゃないでしょうか。
お金と時間の使い方は一人一人が自由に決める権利がありますから、それをみんな保護犬にというのは強引すぎると思います。