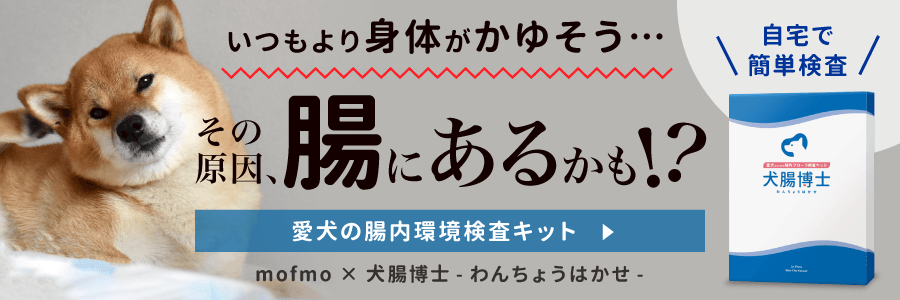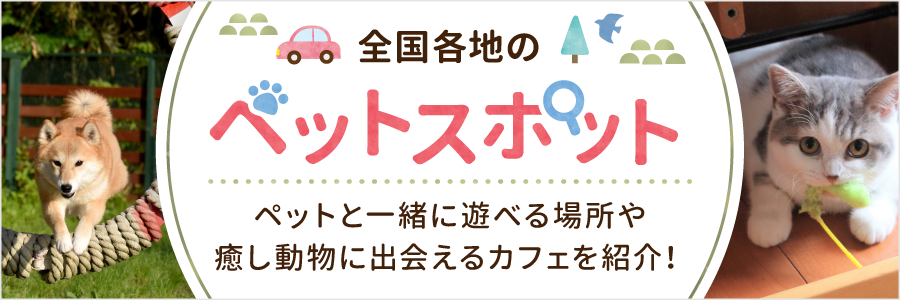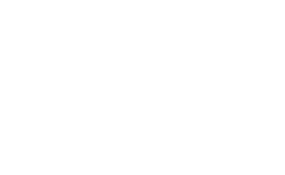猫も寂しいというサインを出している!寂しがり屋の猫への正しい対応を紹介
自由気ままな猫でも人間と同じように寂しさを感じることがあります。今回は、そんな寂しがり屋の猫が出すサインや、甘えてきたときの正しい対処法をご紹介します。適度な距離を保って猫の気持ちを満たしてあげましょう。

一般的に、猫は孤独が平気な動物として知られています。群れで生活することもありませんし、絶えず飼い主さんの側にいようとするわけでもありません。
それでも、猫の中には寂しがり屋のタイプもいます。また、寂しがり屋というほどではなくても、時に寂しさを感じることがあります。
今回は、猫が感じる寂しさに焦点をあてて、飼い主さんとして助けになれる点をいくつかご紹介します。猫が寂しくなったときのサインや、寂しがり屋の猫にどのように対処すべきか解説します。
寂しがり屋の猫

pixabay.com
猫は単独行動することが多いので、あまり寂しさを感じていないように思えます。
実際はどうなのでしょうか?寂しさを感じる猫について解説します。
猫は完全な孤独を好まない
同じように一般的なペットである犬と比べると、猫はどうしてもマイペースなイメージがあります。実際に、猫は一匹で過ごしている時間も多いです。
それでも、完全に孤独を好むというわけではありません。どんな猫でも飼い主さんからの愛情を欲しています。
ただし、ほとんどの猫は「べったり」とした愛情よりも、「適度」な愛情と関係を好みます。
寂しさを感じる程度は個体差がある
人間と同じで、猫も寂しさを感じる程度には個体差があります。
かなりさっぱりとした性格の猫もいますが、飼い主さんのことが大好きで寂しがり屋の猫もいます。
寂しがり屋の猫は珍しいですが、飼い主さんはそれぞれの個性を大事にして、性格に合ったお世話を行ってあげるべきです。
孤独がストレスにつながることも
猫はある程度の孤独を楽しめますが、孤独な状態が続くとストレスです。猫によっては孤独のストレスで食欲不振になったり、下痢や便秘などの体調不良を抱えたりします。
飼い主さんは猫がストレスを抱えないように、猫が感じる寂しさに常に注意してあげましょう。もちろん、逆に構い過ぎることも猫のストレスにつながるので「適度」が大切です。
猫が寂しく感じたときのサイン

pixabay.com
では、猫が寂しいと感じていることをどのように知れば良いのでしょうか?
ここからは、猫が寂しく感じたときのサインをご紹介します。猫のちょっとした行動に敏感であれば、その寂しい気持ちを埋めてあげることができるに違いありません。
飼い主さんの側にいたがる
自由気ままな猫でも、不意に飼い主さんの近くに寄ってくるときがあります。
飼い主さんがその場から離れても付いてくることもあるのではないでしょうか?これはとても分かりやすい「寂しさサイン」です。
鳴いて飼い主さんを呼ぶ
成猫はむやみに、あるいは頻繁に鳴いたりすることはありません。ですから、成猫が鳴くことは何らかのサインだと考えられます。
特に、少し低めの声で鳴く場合は寂しさゆえに飼い主さんを呼んでいる証拠です。
飼い主さんの邪魔をする
飼い主さんの行動をなにかと邪魔する猫もいるのではないでしょうか?これも、猫の「寂しさサイン」です。
歩くときやテレビを見るとき、仕事をするときなどに必ず邪魔してくるかもしれません。それは「寂しいから構って!」という猫からのアピールです。
寂しがり屋の猫に対する正しい対応

pexels.com
最後に、寂しがり屋の猫に対する正しい対応をご紹介します。
大切なのは、寂しがり屋の猫が自立できるような仕方で構ってあげることです。
なるべく環境を変えない
猫は自分が住んでいる環境の変化に敏感です。大きく変化してしまうと不安を覚え、それが寂しさへとつながります。
ですから、なるべく生活環境を変化させないようにしましょう。寂しがり屋の猫は環境の変化で大きなストレスを抱えてしまいます。
「いつもと変わらない日常」こそが、猫の気持ちを落ち着かせてくれるのです。
毎日猫とコミュニケーションをとる
毎日のコミュニケーションを大切にしましょう。長時間構ってあげる必要はありません。
一緒に遊んであげたり、ちょっとなでてあげたりなど、定期的で適度なスキンシップこそが猫の不安を取り除いてくれます。
依存させない
猫の寂しい気持ちを埋めてあげることは大切ですが、それだけでは依存させてしまいます。
寂しがり屋の猫や、過去にトラブルを抱えていた猫は飼い主さんに依存しやすくなります。一度依存関係ができあがってしまうと猫の不安はさらに強くなってしまうので、依存させない程度に優しくしてあげましょう。
我慢することを学んでもらう
当然ですが、依存させないためには猫のすべての要求に応えてはいけません。そうするなら要求はエスカレートしていくからです。
猫には我慢することを学んでもらいましょう。飼い主さんのほうも、「猫の要求にすぐに応えたい。なんでも応えてあげたい」という気持ちを我慢すべきです。
-

- 【2023年版】おすすめの犬映画20選!感動映画から笑える作品までご紹介!
- 犬好きの方のために映画を20本厳選しました。感動できる映画から笑える作品、ファミリー向けまで、犬の名作映画を邦画7本,洋画7本,アニメ6本を紹介します。それぞれの映画の魅力やあらすじを短い文章で簡潔に紹介しています。映画選びの参考にしていただければと思います。
- 犬と暮らしたい
-

- 【獣医師監修】犬が口をくちゃくちゃする理由を解説!意外な理由と注意点を解説【2023年版】
- 犬が口をくちゃくちゃと動かしている様子を見たことがあるでしょうか。不思議な仕草なので、普段から気になっている飼い主さんも少なくないと思います。今回は口をくちゃくちゃする理由を紹介します。
- 犬の気持ち
-
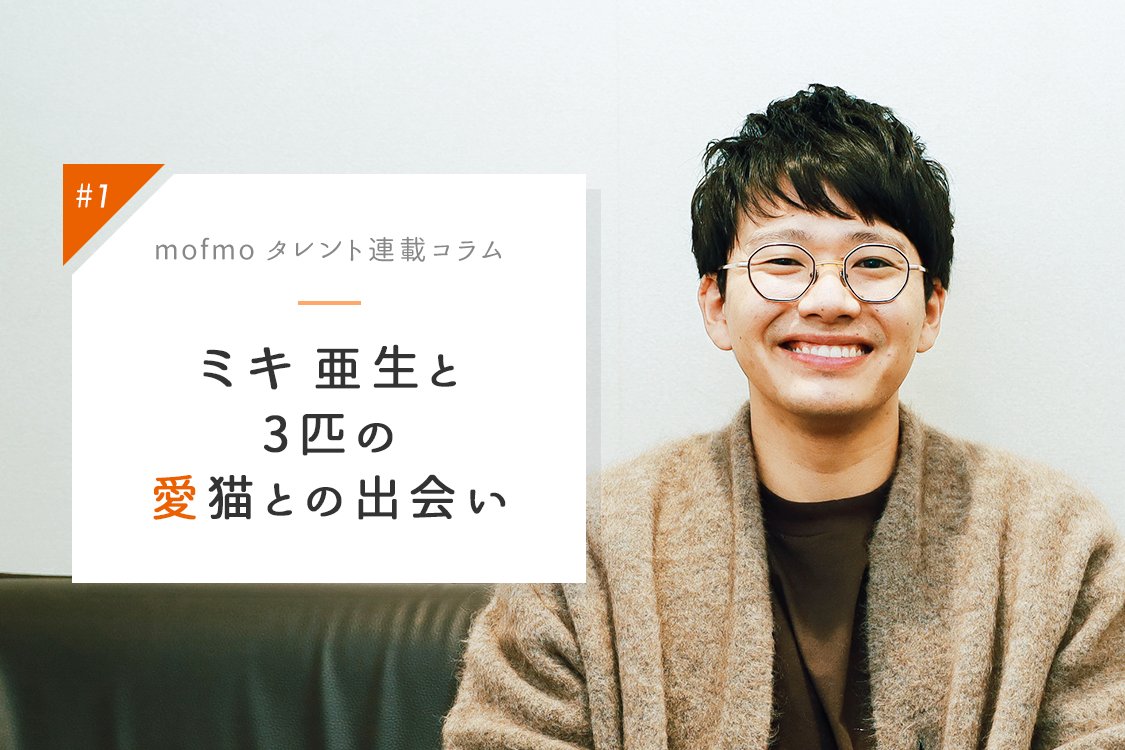
- ミキ亜生(芸人)/第1回 「犬派だった僕が、3匹も猫を飼うなんて夢にも思ってなかったです」
- お笑いコンビ・ミキの亜生さんは、自身が保護した3匹の猫ちゃん「助六(メス)」「銀次郎(オス)」「藤(メス)」と生活をしています。芸人として活躍する傍らで、街で見つけた猫を保護し、里親を見つける活動を行っている亜生さんに、保護猫活動や猫たちとの生活についてインタビューしました。
- お笑いタレント
-

- ペット同伴できる会社がある!?『ペットフレンドリーオフィス』があるマース ジャパンに行ってきた!
- 「カルカン」「シーバ」等のペットフードや「スニッカーズ」「M&M'S」のお菓子でも知られているマース インコーポレイテッド。日本の拠点であるマース ジャパンでは「ペットフレンドリーオフィス」というペット同伴出社が可能な制度があるんです。
- 犬と暮らしたい
-

- 【2023年版】猫を飼っている芸能人・有名人を男女別にご紹介!
- “猫好き”を公言している芸能人もたくさんいますよね。テレビを見ると、ニャンコを飼っている芸能人も意外に多い気がします。そこで今回この記事では、猫ちゃんを買っているジャニーズや芸能人を男女別に10選ずつご紹介します。かわいい愛猫の写真にほっこり癒されること間違いなしです♪
- 猫と暮らしたい
- コメント
1
-

- 【2023年版】夏にピッタリ?!話題のライオンカットとは?猫へのメリットと危険について解説
- 暑い時期が近づいてくると、暑さ対策が話題になりますよね。夏の時期が近づくと、愛猫の被毛を短くカットしたいと思うかもしれません。最近ではその一環でライオンカットというものが流行っています。ここではライオンカットの方法やメリット、さらにその危険性などについても扱いたいと思います。
- 猫のお手入れ
-

- 【獣医師監修】猫に菜の花はNG?猫草代わりとして与えてもダメ?注意点やリスクを解説【2023年版】
- 春になると鮮やかな黄色の花を咲かせる菜の花。独特のほろ苦さと香りが魅力なことから鑑賞以外に食用としても人気の菜の花ですが、猫が食べても大丈夫なのでしょうか?この記事では猫に菜の花を食べさせる場合にどんな点に気を付けたらいいのかを解説します。また猫草代わりに菜の花を与える際に注意したい点も説明します。
- 猫の食べ物
-

- 【獣医師監修】猫にレンコンを与えても大丈夫?含有している栄養素や猫へのメリットをご紹介!【2023年版】
- 小鉢料理などで活躍するレンコンは、日本人にとってなじみの深い野菜の一つです。栄養素も豊富なので、愛猫にも与えようかどうか迷っている人も多いでしょう。でもレンコンは野菜なので、肉食の猫には与えても大丈夫なのか心配な人も多いはず。そこで今回は猫とレンコンの相性について調べてみました。
- 猫の食べ物
-

- 【2023年版】猫がゴロゴロ・クネクネ転がるのはなぜ?!理由や猫の心理を解説
- 猫は警戒心の高い動物のはずなのに床でゴロゴロ転がっていたり、仰向けで爆睡したり、へそ天状態でクネクネしたり、急所であるはずのお腹を丸出しにしたりすることがあります。そんな猫の行動には、本能に基づく理由やその姿を見せている相手に伝えたい気持ちが込められています。ここではそんな猫の心理をご紹介します。
- 猫の気持ち
mofmo掲示板
-

- 赤ちゃんにやきもちをやく愛犬
- この度、飼い主の私が出産し、新しい家族がふえました。 新生児の赤ちゃんにやきもちを焼き、頻繁に吠えるようになりました。 新生児の世話、家事、で手いっぱいで、出産前のように頻繁に散歩に連れていけない 状況です。ストレス発散させる方法はありますか?
- コメント
便利屋さんにお散歩代行を頼むとかはどうかな?何度か来てもらってペットに慣れてもらって、公園でたっぷり遊んでもらう。もしくはベビーシッターを頼んで赤ちゃんを預けて犬と遊んであげる。家事代行を頼んで家事の時間をペットに充てるとか。
-

- ペット保険、夫婦で意見がわれています。皆さん加入していますか?
- 皆さんはペット保険加入していますか? 加入を私は考えていますが、旦那が必要ないのいってんばり。 理由は、過去に実家で飼っていた犬は病院にかからなかったということです。 犬種は、ダックスフンドのオス2歳です。
- コメント
加入してますよ!人間と同じです。何かあってからでは遅いですし、なかったらなかったでそれは幸せなことです。それでもったいなかったなぁなんて思わないでしょ?
-

- 今度ドックランデビューします!マナーをおしえてください!
- ドックラン特有のマナーってありますか?飼い主のわたしが、緊張してます。
- コメント
マナー?自由奔放に走り回らないように周囲の邪魔にならなければいいと思いますよ。証明書とかはもちろん必要ですけど、それはマナーとは違いますよね