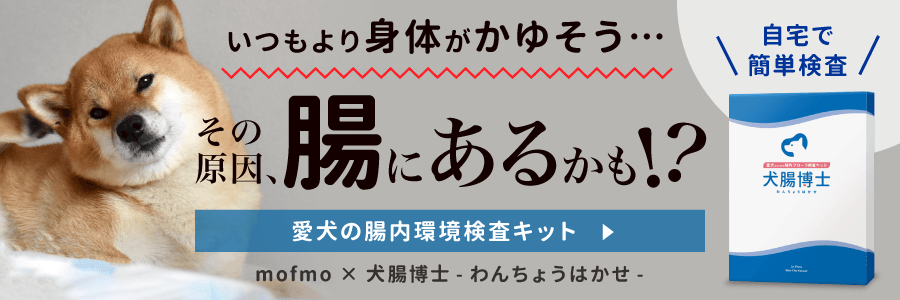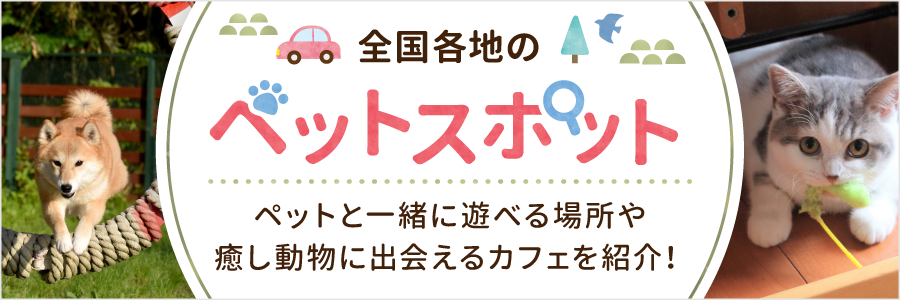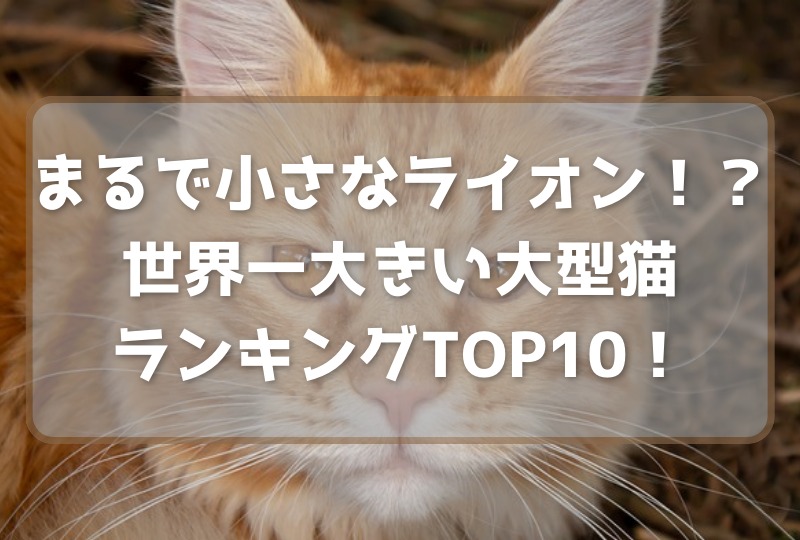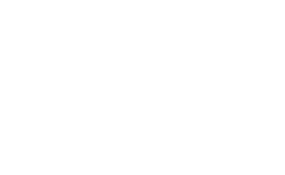カレリアンベアードッグってどんな犬?性格と特徴から考えるしつけと飼い方のコツ!

mofmo編集部です。
フィンランド生まれの狩猟犬であるカレリアンベアードッグは、日本犬によく似たスピッツタイプの犬です。また、勇敢な犬で他の犬やペットに対して攻撃をしてしまう為にコンパニオン・ドッグとして飼育する事は難しい犬種とされます。今回は、カレリアンベアードッグについて紹介していきたいと思います。

カレリアンベアードッグの特徴

Perinbaba/shutterstock.com
カレリアンベアードッグ(Karelian Bear Dog)は、フィンランドとロシアの国境地帯にあるカレリア地方で作出された犬です。
体重が17~28㎏、体高が52~60㎝ほどの大型犬に分類される犬です。
原産国であるフィンランドでは国宝にも指定されているほど、有名であり歴史を持つ犬種です。
「ベアードッグ」と名前にある通り、クマの狩猟犬として作出され、活躍していました。
単独でも、小さな群れとしても猟をすることができ、獲物を見つけると大きな声で吠えます。
そして、獲物を追いかけて噛みつき獲物が逃げないようにしました。
このように、勇敢で噛む力がとても強いことが特徴の一つです。
クマだけでなく、シカやイノシシの狩猟も行います。
現在でも、そのような大きな動物のハンティングをしている実猟犬です。
家族への愛情は深く、自分がリーダーと認めたものに対しては忠実で服従します。
もし、家族への危険を感じた場合には、自分の身を危険にさらして命をかけても守ろうとする勇気があります。
それで、ガードドッグとしても活躍しているカレリアンベアードッグもいるようです。
北欧ではペットとして、さらにショードッグとしても愛されています。
カレリアンベアードッグの外見的特徴
カレリアンベアードッグの容姿の特徴としては、日本犬に似たスピッツタイプの犬という特徴があります。
また、被毛はスムース・コートですが、防寒性や防水性に優れているので、寒い場所や水の中でも作業する事ができます。 全体的に筋肉質の体格をしていますが、その中でも最も特徴的な事は噛む力が強い事です。
一般的に噛む力は約100㎏あるとされ、噛まれると大怪我をする事は間違いないので、しつけによって噛み癖を徹底的に矯正する必要があります。
カレリアンベアードッグはよく笑っているような顔をしていますが、口角が少しあがっていることでそう見えるようです。
大きくて立派な立ち耳と、クルンと上に巻いた尻尾もトレードマークです。
聡明な目を持ち、利発なカレリアンベアードッグが理想的とされています。
カレリアンベアードッグの寿命・体型
巻尾で立ち耳で、日本犬に似ている姿をしているので、日本人にとっても親しみやすい見た目の犬種 だと言えるでしょう。
がっしりとした骨格に、筋肉質の体つきをしています。
引き締まっていて、脚にも筋肉がしっかりとつく体型です。
オスの場合、体高は54~60cmほどにもなり、体重も25kg以上になります。
メスはそれより少し小さめで、体高が49~55cmほど、体重は17~20kgほどです。
自信があり勇敢な姿は、とても立派で清々しさも感じさせます。
寿命は、11~13年くらいです。
このサイズの犬としては、平均的な寿命と言えますね。
もともと活発でたくさんの運動量を必要としますので、運動欲を満たしてあげることや、できるだけストレスのかからない環境と飼育を行うことで、できるだけ元気に活発に過ごしてくれることでしょう。
カレリアンベアードッグの歴史

Tiina Tuomaala/shutterstock.com
カレリアンベアードッグの起源に関する詳細はよくわかっていません。
しかし、数百年前にロシア人によりフィンランドに持ち込まれた、と言われています。
古くから、カレリア地方のハンターに好まれ、数多くの個体が飼育されてきて、狩猟犬として活躍してきました。
もともとは被毛のバリエーションが様々ありましたが、暗闇の中や雪の中でもしっかりと見分ける事ができるようにする為に現在の被毛のカラーであるブラックとホワイトの特徴的なカラーとなりました。 カレリアンベアードッグは、犬種名にあるようにベアー、熊に対する狩猟犬として改良された犬です。
かつては、日本にも軽井沢や北海道で熊被害が出た際には呼び寄せたほどの、熊に対する高い狩猟能力を持つという特徴を持った犬です。
また、熊以外にもエルクやイノシシといったほかの大型獣に対しての狩猟でも活躍しています。 フィンランドとロシアの国境地帯で生まれた犬なので、1900年代になるとロシアとフィンランドで故郷問題が起こるとどちらの国に帰属させるかについて論争が行われるようになりました。
最終的には2カ国で1つの犬種を分断所持するという結果となりました。 ただ、無計画な異種交配によって純血の個体が減少してしまい、絶滅に瀕しましたが、愛好家の尽力によって絶滅を免れる事に成功しました。
1945年に正式なスタンダードが設定され、FCIにも公認されました。
-

- 【2023年版】おすすめの犬映画20選!感動映画から笑える作品までご紹介!
- 犬好きの方のために映画を20本厳選しました。感動できる映画から笑える作品、ファミリー向けまで、犬の名作映画を邦画7本,洋画7本,アニメ6本を紹介します。それぞれの映画の魅力やあらすじを短い文章で簡潔に紹介しています。映画選びの参考にしていただければと思います。
- 犬と暮らしたい
-

- 愛犬と一緒に出社する夢を実現した富士通『ドッグオフィス』に行ってみた!
- “愛犬と一緒に出社する” ワンちゃんを飼っている社会人なら憧れる人も多いのではないでしょうか。そんな夢のような取り組みを富士通は大手企業ながら実現してしまいました。富士通が愛犬家のためにどんな取り組みをしているのか新たに設立された【ドッグオフィス】を取材してきました!
- 犬の生活
-
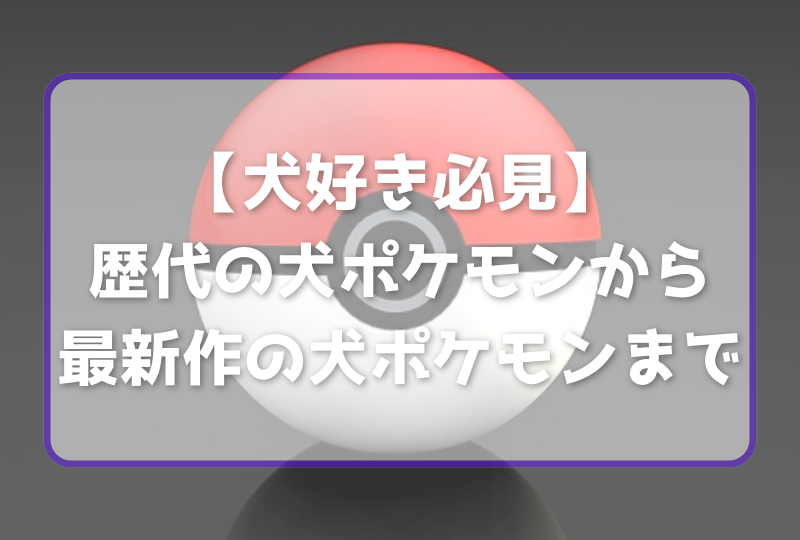
- 【犬好き必見】歴代の犬ポケモンランキング!最新作の犬ポケモンまとめてご紹介!
- 11月18日にポケモンシリーズ最新作「ポケットモンスタースカーレット」「ポケットモンスターバイオレット」が世界同時発売しました。そこで、今回は「歴代の犬ポケモン総まとめ」をお送りします。今までポケモンに興味がなかった方も、可愛くてかっこいい犬モチーフのポケモンにメロメロになっちゃうかも。
- 犬種図鑑
-

- 【獣医師監修】犬が口をくちゃくちゃする理由を解説!意外な理由と注意点を解説【2023年版】
- 犬が口をくちゃくちゃと動かしている様子を見たことがあるでしょうか。不思議な仕草なので、普段から気になっている飼い主さんも少なくないと思います。今回は口をくちゃくちゃする理由を紹介します。
- 犬の気持ち
-

- 【2023年版】ポメコギってどんな犬?性格と特徴から考えるしつけと飼い方のコツ!
- 純血の犬たちの性格や容姿など、犬種ごとに様々ある気に入った部分や特徴をかけ合わせた犬がいたらいいな、と考えている人も多いのではないでしょうか?昨今ミックス犬という純血種の犬をかけ合わせた犬種が登場しておりとても人気があります。ここではポメラニアンとコーギーのミックス犬についてご紹介していきます。
- 犬と暮らしたい
- コメント
うちにポメコギがいますが、このサイトのトップ画は間違いなく純コーギーではないかと......うちの子は、耳はポメ寄り、マズルと目はコギ寄りで、短足長毛です。 とりあえず、ポメコギの紹介ページで使うならば、ちゃんとしたポメコギちゃんを使って欲しいです......
-

- 【2023年版】シバーギーってどんな犬?性格と特徴から考えるしつけと飼い方のコツ!
- 純血の犬たちの性格や容姿など、犬種ごとに様々ある特徴をいいとこ取りしたミックス犬が昨今話題になっています。 その中でも特に人気があるのは、柴犬やチワワ、コーギーなどの飼いやすくて容姿がかわいい犬を掛け合わせたミックス犬です。 ここでは人気の柴犬とコーギーのミックス犬についてご紹介していきます。
- 犬と暮らしたい
- コメント
私は、10年前に知り合いからシバギーを頂き飼って居ました。初めて見たときは柴だ、柴だと思っていましたら?足が短くて、初めてシバギーと分かりました。散歩が大好きで余り吠えない犬でした。でも?病気に成り亡くなりました。頭が良く聞き分けの良い犬でしたよ。
-

- 【2023年版】アメリカンブリーってどんな犬種?性格や特徴、飼い方まで詳しく解説!
- アメリカンブリーという犬種についてあまり聞いたことがないかもしれませんが、これから人気が爆発する可能性が大なので注目です。しかし、よく見るとピットブルに似ているアメリカンブリーですが関係はあるのでしょうか?ここではアメリカンブリーの歴史や身体的特徴、性格を紹介します。
- 犬と暮らしたい
-

- 【2023年版】トイフォックステリアってどんな犬?性格と特徴から考えるしつけと飼い方のコツ!
- トイフォックステリアはアメリカ合衆国産のテリア犬種のひとつで、日本ではあまり見かけることがありませんが、アメリカやイギリスでは根強い人気のある犬種です。テリアキャラクターを持ってはいるものの、セラピードッグとして活躍している犬種でもあります。そんトイフォックステリアの特徴や飼い方のコツを紹介します。
- 犬と暮らしたい
-

- 【シーズーってどんな犬?】シーズーの性格がわかる3つの行動!【2023年版】
- 見た目もかわいく、愛嬌のあるシーズーを一度は家族に迎えてみたいですよね。 見た目通り性格も穏やかで陽気。その上とってもノンキなので高齢者の方でも一緒に生活することができる素敵な犬種です。でもその反面とっても頑固な一面もあるんですよ!
- 犬と暮らしたい
- コメント
写真がシーズーじゃないと思うんだけど‥。
mofmo掲示板
-

- マルチーズを飼っていますが、涙焼けがひどくどうしたら除去できるのでしょうか?
- こまめに目の周りを拭いていますが、涙焼けがひどくなる一方です。
- コメント
うちの子はチワワですが、1、2才の頃まで涙焼けがひどかったです。ただドライフードを替えたり、出来るだけ手作りのご飯に替えたりしてみると、その後ずっと涙焼けしなくなりました。
-

- 家を出るときに「行かないで」と吠えて訴える愛犬
- 家を出るときに「行かないで」と吠えて訴えてくれていると、私は思っているにですが 犬って実際はどう思って経ているのですか?言葉が話せればなーって考えてしまいます(;^ω^)
- コメント
家を出る時に必ず玄関まで送りに来てくれますね。行ってらっしゃい、気をつけてって言ってるのかなと思ってます。
-

- 犬に芸をやらせたい!
- 何か犬に芸をやらせたいです。
- コメント
12歳の犬でも覚えることは、できますか?